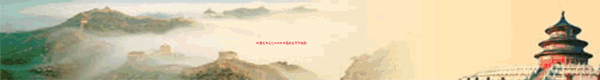|  2006年9月、賈樟柯監督の新作『三峡好人』が、ベネチア国際映画祭の最高賞である金獅子賞を獲得した。 2006年9月、賈樟柯監督の新作『三峡好人』が、ベネチア国際映画祭の最高賞である金獅子賞を獲得した。
賈樟柯監督は張芸謀や陳凱歌など「第五世代」監督より世代が一つ下の「第六世代」にあたる。これまで一貫して中国の市井の生活に注目し、シンプルな映像によって彼らの喜びや苦しみを記録してきた。賈樟柯監督の映画はヒットをとばす大作ではないが、これに心酔する若者は多い。自分たちの生活が如実に再現されているからだ。
今回、本誌のインタビューに答え、『三峡好人』の製作過程におけるさまざまな思いを語った。
三峡の人々は積極的に生きている
 ――どうして『三峡好人』を撮ったのですか。 ――どうして『三峡好人』を撮ったのですか。
賈樟柯監督(以下、賈と略す) 実は偶然からなのです。私の友人である画家の劉小東さんが三峡へ行って三峡の工事現場で働く作業員を描くことになりました。すると、彼の創作過程を記録するドキュメンタリー映画(編注・この映画『東』もベネチア映画祭のオリゾンティ部門に出品された)を私に撮ってほしいという希望が出たのです。そこで私は三峡へ行くことになりました。
私が三峡へ行ったのはこれが初めてです。三峡地区の人々の生活は私の心を非常に揺さぶりました。このときにはもう、『三峡好人』を撮ろうと考えていました。
 ――なにがあなたの心を揺さぶったのですか。 ――なにがあなたの心を揺さぶったのですか。
賈 三峡の農村の人々の生活はとても大変だと思いました。
私の故郷の山西省もところによってはとても貧しいのですが、どんなに貧しくても家には年画が飾れますし、テレビもあります。置時計もあります。
しかし、重慶市の東北部に位置する奉節県の山の中の生活は、赤貧洗うがごとしです。泥の壁にたんすが一つ、腰掛が一つ、かまどが一つあるだけで、ほかには何もありません。
また、まだ適当な場所に落ち着いていない三峡の移住民たちは、橋の下に住んでいます。本来は洪水の際に水をはくために作られた空洞をふさぎ、一時的な家にしています。彼らの姿を見て、人は草と同じようにどこででも生きていけるのだなあと思いました。
 ――深く印象に残った人はいましたか。 ――深く印象に残った人はいましたか。
賈 あるとき、「老鬼」と呼ばれている作業員を撮りました。彼は手で粗く巻いたタバコをいつも吸っていて、周りはむせてしょうがなかった。しかし私は彼に好印象を抱いた。彼は何を聞いても笑っていました。暗くなると一人で家へ帰っていくのです。私は彼が私のファインダーから去っていくまでずっと撮影していました。
あとになって、彼は家へ帰ってから何をしていたのか、彼にはどんなプライバシーや感情があったのかと考えました。こういったことを私は何も知りませんでした。ドキュメンタリー映画でもとことんまで追求しませんでした。しかしこれにより、私の『三峡好人』に対するイメージは形作られたのです。
 ――三峡の人々はあなたがこれまでに出会った人々とはかなり違うようですね。 ――三峡の人々はあなたがこれまでに出会った人々とはかなり違うようですね。
賈 かなり違います。たとえば、中国人はメンツを大切にします。お金がなくても、荷担ぎ人夫になりたいとは思いません。でも三峡地区の人々は違います。彼らはお金が必要であるからには、稼ぐべきだと考えるのです。ある客引きの男の子は、宿は必要ないか、食事はどうだ、車に乗らないかと何度も何度も飽きることなく尋ねてきました。実のところ、彼の家が店をやっているわけではなく、客引きの仕事でお金を稼いでいたのです。
 また、長江のほとりで荷物担ぎの仕事をする「棒棒」たち。彼らが一回の仕事で手にするのは1角か2角です(1角は1元の10分の1、約1.5円)。それでも彼らは積極的に自らの生活を改善しようとしているのです。 また、長江のほとりで荷物担ぎの仕事をする「棒棒」たち。彼らが一回の仕事で手にするのは1角か2角です(1角は1元の10分の1、約1.5円)。それでも彼らは積極的に自らの生活を改善しようとしているのです。
そこで、『三峡好人』の中では、復縁したカップルと離縁したカップルの物語を描きました。主人公たちは閉鎖的で茫漠とした受身な状態に再び戻ることはなく、能動的に行動し、自分の生活を決定します。
一般の人々の関心は薄い
映画は自由を探求する方法
……(全文は2月5日発行の『人民中国』2月号をご覧下さい。)
|