
夕月や槐にまじる合歓の花
灰捨つる路は槐の莢ばかり
石垣に日照りいざよふ夕べかな
来て見れば軒はふ薔薇に青嵐
右の数首は1921年夏の北京の景観を詠んだ俳句だが、いずれも小説家芥川龍之介の手になるものである。中には、彼が北京から友人に送った手紙に書かれたものもあるし、後日発表したものや生前未発表のものもある。『羅生門』や『杜子春』などの人口に膾炙する名作を残した芥川龍之介は、実は俳句の名手でもあり、また、北京を句題にした俳句を書いたことは、中国でも日本でも知る人は意外に多くない。
1921年に大阪毎日新聞社から中国視察旅行に派遣された芥川は、江南地方や長江流域の都市をひととおりまわった後、北京に約1カ月間滞在した。この悠久の古都ののどかな風情に、彼はすっかり魅せられたのである。今年2007年は、ちょうど芥川の没後80年にあたる。そして、彼のこよなく愛した北京は、一年後のオリンピック開催に向けて、21世紀の国際的大都会へと目覚しい変貌を刻一刻と遂げている。しかも現在、大手書店を覗いてみれば幾種もの芥川作品集が目につくように、中国で芥川作品の出版ブームが起きている。
 |
| 芥川龍之介(左)、1921年北京にて |
こうした背景の中で、北京に惚れ込んだ東京生まれの天才小説家の86年前の北京との出会いを振り返るのは、もっとも時宜を得ていると言えよう。このような趣旨で草したこの小文をもって、今年の中日文化・スポーツ交流年並びに芥川龍之介没後80年に捧げ、そして来年は世界的な大イベントの中心舞台となる北京に、ささやかな祝福を送りたい。
芥川龍之介が北京に入ったのは、1921年6月である。時期はちょうど初夏に入る頃で、彼はすぐに中国式の夏服を一式あつらえた。そして、毎日のようにそれを着て出かけ、中国民俗学者中野江漢の案内のもと、北京の街を隅々まで歩き回ったのである。万寿山(頤和園)、玉泉山、北海、天壇、地壇、先農壇、雍和宮、什刹海、陶然亭、白雲観、永安寺(北海公園内)、天寧寺……。その見学の熱心さと徹底ぶりは、北京に長く住んだ中野江漢を驚嘆させるばかりだった。
「花合歓に風吹くところ支那服を着つつわが行く姿を思へ」。この自作の歌は、初夏の北京を心より楽しんでいた小説家の様子を髣髴とさせる。
芥川が語った北京の印象には、必ずと言っていいほど、槐や合歓などのイメージが出てくる。例えば後に中国旅行記の『支那游記』に収められた「雑信一束」には、「北京」と題する次のような一節がある。
甍の黄色い紫禁城を繞つた合歓や槐の大森林、――誰だ、この森林を都会だなどと言ふのは?
紫禁城を中心とする当時の北京は、「森林」としてその眼に映ったのである。鬱蒼とした大樹が黄色の瑠璃瓦を幾重にも取り囲んだ風景は、北京の城壁の上から眺めたものと思われるが、当時の北京は市民一人当たり三本の樹木を擁するほどの文字通りの「森の都」であった。高層ビルと立体交差で埋まる現在の北京からは想像もつかない古都の、今ではもはや失われてしまった姿が記述されている。
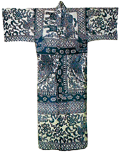 |
| 死の床で着ていた浴衣(新潮社刊『新潮日本文学アルバム 芥川龍之介』による) |
明清二代王朝の皇帝の住まいである紫禁城が故宮博物院となったのは1925年のことで、1921年当時は、遜位したラストエンペラー溥儀がまだ内廷で暮らしていた。紫禁城の外朝の一部、文華殿と武英殿だけが「古物陳列所」として開放され、民国政府の所有する文物を展示していた。そこの見学には筆記用具の持ち込みが禁じられていたため、芥川は見学後に記憶に頼って、眼にした古代書画を手帳に書きとめた。それによれば、唐・閻立本「職貢図」、元・王蒙「長松飛瀑図」、明・文徴明「古木寒泉図」、清・銭維城「林泉雨景図」など、歴代王朝の名品があったことがわかる。また、中国書画に高い鑑識眼を持つ芥川は、展示品の中に贋作が混じっていることも見抜いていた。
しかし書画の鑑賞という面でより芥川の眼を開いた場所は、古物陳列所よりも、西単の霊境胡同にあった陳宝陦の家であった。陳宝陦は清末の重臣で、溥儀の師匠に当たる人物である。彼自身も書画に長け、書画の収蔵家でもあり、なんと紫禁城宮内の元乾隆帝の収蔵品まで所有していた。訪ねてきた芥川の前に、陳宝陦は数々の珍品を惜しみなく持ち出して、芥川をしてすっかり瞠目させた。その中には、李公麟「五馬図」、宋徽宗「臨古図」、王時敏「晴嵐暖翠図」、郎世寧「百駿図」などが含まれていた。これら中国古代芸術の精髄と言ってもいい品々に芥川は感動し、友人にも「此処の御府の画はすばらしいものです」と伝えている。陳宝陦宅で芥川が鑑賞した書画はやがて散逸し、その多くが所在不明となっている。北京城内の胡同にある一軒の居宅で、これほど多くの名品を一斉に眼にすることは、もはや不可能である。その意味では、芥川龍之介は相当恵まれた旅行者だったとも言える。
名所見学と書画探訪のほかに、芥川は中国戯曲の鑑賞にも熱中した。彼自身の言葉でいえば、北京へ来てからは「速成の劇通になった」ほどほぼ毎日劇場に出入りし、「芝居まわり」をしていた。しかも滞在中観た芝居は、「六十有余」にも上るという。1920年代では、京劇という名称こそ定着していなかったものの、戯曲はもっとも主要な大衆娯楽であった。後に四大名旦と称される女形の名人梅蘭芳、程硯秋、尚小雲、荀慧生たちが頭角を現した頃で、この四大名旦はもちろんのこと、楊小楼、余叔岩、カク寿臣、貫大元など、京劇の全盛時代を飾る数々の名優の演技を、芥川は観たのである。ちなみに、梅蘭芳と楊小楼一代の当たり役となった京劇『覇王別姫』は、この年に北京で初演された。
 |
| 芥川龍之介(右)、1921年北京にて |
芥川の旅行記には、同楽園で崑曲の名優韓世昌の演じる『火焔山』と『胡蝶夢』を観た詳細な記述が見られる。500年の歴史を持つ崑曲は中国に現存する最も古い戯曲であり、長い間、貴族や文人の間で愛好されていたが、清末以降急激に衰退し始めた。前門外の大柵欄の胡同の中にある同楽園は、当時崑曲を上演する唯一の劇場であった。
同楽園に足を運んだ芥川は、ある酔顔の老人と遭遇した。同行者が、「あれは樊山だ」と教えた。樊増祥(号は樊山)は、清末民初の名高い文人で、生涯にわたって日常茶飯事的に詩を作り、詩作3万首、駢文百万言を残した当代きっての詩宗であった。民国時代には遺老として閑居し、詩酒と観劇を嗜む晩年を送った。劇場で不意に遭遇したこの老詩人に、芥川は「僕は忽ち敬意を生じ、梯子段の中途に佇みたるまま、この老詩人を見守ること多時」「文学青年的感情は少く(全集の原文ママ)とも未だ国際的には幾分か僕にも残りをるなるべし」と書いている。「国際的」「文学青年的感情」、つまり海外の文学ファンが持つような気持ちが思わず湧いてきたということであろう。劇場というもっとも市井的な空間において、昔ながらの旧派文人の悠々と観劇する一瞬の横顔から、芥川は中国の伝統的な詩文精神の一端を垣間見たのである。
この日、崑曲を見た後の夕方には、中国の新世代知識人の代表者胡適を招待することになっていた。アメリカに留学し、帰国後に中国の新文化運動の旗手を担っていた胡適は、当時北京大学で教鞭をとっていた。胡適日記によると、彼もちょうど芥川より一カ月前に、同じく同楽園で崑曲を見たばかりであった。しかし、伝統戯曲に対して、あいにく胡適はほぼ全面的に否定する立場を取っていた。芥川龍之介は胡適との席上で、多少の意見を保留しながら、伝統戯曲の改良について英語で滔々と見解を述べ、胡適を感服させた。胡適日記には、中国式の服を着た芥川が中国人に酷似し、言うことも相当の見識を持っていたという、芥川についての印象が記されている。この年、芥川龍之介は29歳、胡適は30歳であった。
 |
| 芥川龍之介『支那游記』の中国語翻訳(左は陳生保・張青平訳、北京十月文芸出版社2006年1月、右は秦 剛訳、中華書局2007年1月) |
日本へ帰る前に、芥川は天津も訪れたが、天津のような西洋風の街に来るとたちまち北京への「郷愁」を感じた、と述べている。東京に住むことがかなわずとも北京に住むことができれば本望、という思いを抱いたほどであった。芥川は、北京を離れる直前に、ある雑誌社のインタビューに、次のように答えている。
「私が支那を南から北へ旅行して廻った中で北京程気に入った処はありません。それが為に約一カ月も滞在しましたが、実に居心地の好い土地でした。城壁へ上って見ると幾個もの城門が青々とした白楊やアカシヤの街樹の中へ段々と織り出されたように見えます。処々にネムの花が咲いて居るのも好いものですが殊に城外の広野を駱駝が走って居る有様などは何んとも言えない感が湧いて来ます」
このような北京へのノスタルジックな愛着を芥川は持ち続け、北京の旅から4年過ぎた1925年にも東京日日新聞で、「僕のあるいて一番好きな所といったら北京でしょうね。ふるい、いかにも悠々とした街と人、そしてあらゆるものを掩いつくす程の青青とした樹立、あれほど調和のとれた感じのよい都はないと思います」と、懐かしげに語っている。帰国後は多忙な作家生活を送った芥川は、もう一度北京へ行きたいという思いを果たすことなく、1927年の夏に36歳の若さで自殺する。死ぬ時には聖書を枕元に置き、中国で買い求めた浴衣を着ていた。
 |
| 2003年以後、中国の各出版社から刊行された芥川作品集 |
芥川龍之介が亡くなって80年を経た現在、その文学が中国で愛読されている。2005年に全5巻本の中国語版『芥川龍之介全集』が刊行されたが、これは中国で刊行された最初の日本人文学者の全集であり、また海外で出版された最初の芥川全集でもある。さらにその刊行後、芥川作品の出版の勢いによりいっそう拍車がかかり、「挿絵版」「普及版」「経典版」「保存版」などの形で、数々の新版作品集が次々と書店に並ぶようになった。この現象を見る限り、芥川文学の芸術性と国際性が改めて認知されたと言える。しかしそれは同時に、世界の優秀な文化遺産を自由に享受する精神性や国境を越えた広い視野を持つ若い世代が、中国で育ったことの証でもあると考えられる。中国の芥川ブームの牽引力となったのは、これらの青年層の読者たちの存在なのである。
また喜ばしいのは、中国の大学における日本研究専攻の大学院課程の充実に伴い、芥川龍之介を学位論文の研究テーマに選ぶ学生も増え、優秀な新鋭研究者が数多く育てられていることである。こうした状況の中、芥川龍之介国際学会の第二回大会が、まもなく寧波大学で開催される。世界的に評価されている天才小説家の没後80年に、この国際的シンポジウムが中国で開催されることは、極めて大きな意味を持つであろう。世界一の人口と急速な近代化への歩みを誇る国で、芥川龍之介文学の国際化が確実に遂げられている。