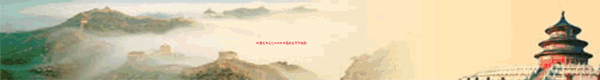
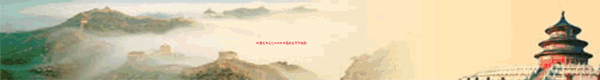 |
|
知られざる敦煌・楡林窟
|
|
時超えて舞う飛天の美
|
|
趙声良
|
一般に言う飛天とは、八部衆(仏法を守護する八種の下級神)の乾闥婆(香音神)と緊那羅(音楽天)を指している。それぞれ音楽と歌舞を司る神で、仏教経典では、仏が説法する際に天から舞い下りてきて音楽を奏し、舞いながら花をまき散らして仏を讃えると記されている。 敦煌壁画の説法図や経変図には、数多くの飛天が描かれている。楽器を奏でるもの、仏の功徳を讃嘆するもの、花をまき散らすものなど、その姿は実に多彩だ。 飛天はインドの仏教芸術にも早い時期から登場するが、中国ほど普遍的に見られるものではなかった。インドの飛天が金剛力士のような逞しさを持っている一方、中国の飛天は仙人のような軽快さに満ちている。仏教は中国に伝来して以来、神仙思想と融合しつつ特有の形態やイメージを持つようになったが、飛天もまた、中国古来の「飛仙」と結びついて本来の姿を変えたのだった。 中国ではほとんどの仏教石窟や寺院で飛天の姿を見ることができる。楡林窟も例外ではなく、各時代の壁画にはそれぞれ風格の異なる飛天が描かれており、独特の魅力を放っている。以下に、各時代の飛天芸術の特徴を紹介していくことにしよう。 中唐期の飛天は、第15窟の前室に見ることができる。南北の壁に展開する天王図に、天から舞い下りて仏を讃える飛天の姿が描き込まれている。南壁の天王は弓を持ち、爛々と光る目で前方を見つめており、実に雄々しい風格に満ちているが、その前方で香炉を手に跪座する飛天の姿が画面の緊迫感を和らげている。 
第15窟には天王図のほかに、天井部分にも二体の飛天が描かれている。こちらの飛天はやや大柄で、一体は一心不乱に笛を吹き、もう一体は鳳首クゴという弦楽器を弾いている。いずれも美しい調べに陶酔しているかのような、満ち足りた表情をしている。波打つ天衣はゆったりと空中を舞う飛天の動きを伝え、洗練された線描、ひかえめで調和の取れた色彩が唐代芸術のおおらかな世界を現出させている。 第25窟も同じく中唐期に造られた石窟で、飛天の姿は少ないが、画師の技巧の高さには目を見張るものがある。そこに描かれた経変画は壁画芸術のひとつの到達点を示すものと言えるだろう。北壁の弥勒経変では、宝蓋(仏の頭部を飾る絹の傘。天蓋ともいう)を挟んで二体の飛天が天空に駆け上がる姿が描かれている。両手を広げた飛天と蓮の花を手に上半身を露わにした飛天は、いずれもスカート状の天衣を着て、長い帯がうずを巻くように漂っている。二体の飛天の外側にはさらに別の飛天がおり、こちらは逞しい体つきで、はつらつとした印象を与える。背景には自然の風景が描かれており、遠方に緑茂る山、手前に滔々たる川の流れが見える。聳え立つ峰々によって画面に奥行きが生まれ、本当に飛天が天空を舞っているように見える。 五代の石窟では天井に飛天を描いている例が多く、飛天のほっそりとした体と長い帯の曲線が、藻井(飾り天井)の図案とよく調和している。第16窟もそうした石窟の一つで、藻井の周りに多くの飛天が描かれている。雲に乗って互いに連なるように舞う飛天たちの手には、琵琶や排簫などの楽器、あるいは花や供物などが握られている。表情や姿態の異なる飛天たちが、天衣を風になびかせながらたおやかに舞う姿は、なんとも魅力的だ。 
多くの説法図や経変図では、仏の頭部にかかる菩提宝蓋の両脇に二体あるいは四体の飛天が配置され、画面に装飾的な効果を添えている。第26窟北壁西側の浄土変にも、宝蓋から仏に向かって舞う二体の飛天が描かれている。滑らかに空中に漂うそれぞれの帯が左右対称の桃形の弧線を描き、装飾図案のような視覚効果を生んでいる。 飛天は一部の密教曼荼羅の中にも特色的な姿で描かれている。第35窟の五智如来曼荼羅には五体の仏が描かれ、中央の仏の頭上にかかる雲の上で二体の飛天が片ひざをつき、合掌して仏を拝んでいる。第38窟北壁の東側にある浄土曼荼羅にも、菩提宝蓋の両側に天に昇ろうとする二体の飛天が描かれている。この飛天は天衣を着ておらず、脇を流れる雲だけでその躍動感が表現されている。唐代以降に描かれた飛天では大変珍しいものと言えるだろう。 また、この時代の飛天は、覆斗頂(枡を伏せたような形状の天井)と四方の壁が交わる部分を縁取るように描かれていることが多い。飛天の絵が藻井の図案と組み合わさり、規則性を持った装飾模様のようになっている。第17窟前室の壁画に描かれた飛天もそうした例の一つで、体が長細く、長いスカート状の天衣を着ている。漂う帯もほかの飛天のものよりやや長めだ。色彩は苔色と赤土色がほとんどで、単調といわざるを得ない。 楡林窟が回コツ(骨に鳥)(ウイグル)に支配された時代、石窟はあまり造られなかったが、そこに描かれた飛天は大変個性的だ。第39窟の中心に立つ塔柱と通路の両側には、子供のように愛らしい飛天が描かれている。何本かの帯を体に纏っただけの姿で、軽やかに天空から舞い下り、両手で花をまき散らしている。輪郭は赤土色で描かれ、そこに淡い暈色が添えられている。背景が緑色の雲になっているため、肌の色が際立って見える。 西夏から元代にかけて造られた石窟にはあまり飛天が描かれていないが、第十窟の天井部に残る伎楽飛天は大変優れたもので、その独特の風格は見る人に深い印象を与える。 この壁画の作者は相当に優れた技巧の持ち主で、特に線描の変化には注意を払っていたようだ。人物の表情の描写が実に細かく、服や装飾品などもめりはりの利いた筆遣いでその質感や軽やかさが巧みに表現されている。また、服装の紋や柄の線描には北宋の画家李公麟らの影響が見て取れ、この壁画が宋代以降に現れた新しい画法を受け継いでいることが分かる。色彩の面では、あでやかでありながら全体の調和が失われていない点が特徴的だ。中国飛天芸術の傑作と言うにふさわしい作品である。(2001年5月号より) |