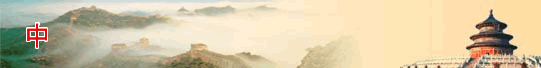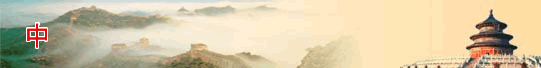『続編四庫全書』は、分散していた文献・資料を整頓、収集したもので、中国の文化人らから後世に恵みを与える盛挙だと言われている。かつては孔子も、一生を費やして『詩経』『書経』『礼記』『易経』『春秋』などの再編集を行った。中国には古代から、このように繁栄の時代に書籍を編集する伝統がある。
清の乾隆年間(1736~1795)には、皇帝の命令により、大型典籍『四庫全書』が編纂された。同書は、乾隆以前の歴代の重要著作を収集し、同時代までの各学問領域の優秀な典籍をカバーしている。そしてのちに、春秋戦国時代から清代までの2000年以上の中国の学術、思想、文化を理解するために欠かせない典籍となった。
時代の推移に伴い、後世の多くの知識人は、この価値ある大型典籍の続編を作ろうと考えた。すでに亡くなった国民党の元将校・張学良将軍も、かつて、1920年代に『四庫全書』の影印、増補、続編の編集を呼びかけたが、戦乱や財力などの各種影響により、目標を達することは出来なかった。
1994年7月、国家新聞出版署及び国家古籍整理出版計画グループの認可を得て、正式に中国の歴史上最大規模の百科叢書『四庫全書』の続編作りをスタートさせた。
『続編四庫全書』の内容は、主に乾隆年間から中華民国成立前の約200年間の中国の伝統学術文化の帰納と総括である。清の『四庫全書』では遺漏、排除などの理由で収録されていなかった文献、いまの価値観では学術的価値のある書籍、当時は異端とされ収録されていなかった戯曲や小説も改めて収録された。新たに収録された書籍はは5000余種にのぼり、計1800冊になった。
同書の編集主幹を務めた著名な古籍研究者である傅せん琮(そう)さんは、この仕事に従事した心境を「深い淵にのぞみ、薄氷を踏む思い」と形容した。
同書の編集に際し、より適切な底本を探すため、編集者は115の国内外の図書館、博物館、個人所蔵家のもとに足を運んだ。歴史とともに、多くの古籍の一部は欠落したが、それらを補ったところ、総計で1万2000ページに達した。より正確な底本を選ぶために編集者たちが注いだ精力は、計りしれない。
『続編四庫全書』は、『四庫全書』の体裁を踏襲し、「経」「史」「子」「集」の4部からなる。一セットを縦に並べれば、72メートルにもなる。販売価格は、38万元の高値になった。(上海古籍出版社)
|