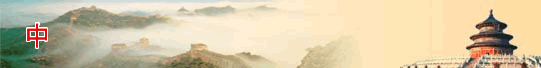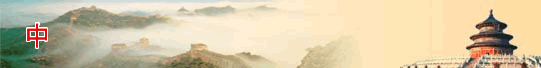|
2002~2003年の『中国農村経済緑書』の公表会とシンポジウムが北京で開かれ、中国社会科学院農業発展研究所の張暁山所長は会議の席で次のように述べた。「3農」(農業、農村、農民)を改善するにはまず資源の配置を改善しなければならない。
第一、「3農」問題は農業、農村、農民そのものの問題であるか、国民経済の持続可能な、健全な発展とかかわりのある問題であるか。中国における資源配置は一部の地域(大都市と沿海地域)の傾斜に力を入れるべきかどうか。新しい成長モデルと新しい発展の道を模索すべきかどうか。
緑書のデータによると、2002年における農民の一人当たり純収入は2476元で、不変価格に基づいて計算すれば昨年より4.8%増えたが、その時点における都市部住民一人当たりの可処分所得は7703元で、実質13.4%増え、都市部と農村部の住民の一人当たり収入の割合は前年の2.89:1から3.11:1まで増え、収入の格差がいっそう大きくなった。その影響を受けて、農村地域の市場消費の伸びもそれに応じて都市部地域より低くなり、全国の消費市場における農村地域の地位は引き続き低下している。
内需を始動させるうえでの最大の問題は農村にあり、農村の消費が盛んでなく、消費市場の始動が難しい根本的な原因は農民の収入レベルが低すぎ、収入の増加は緩慢であることにある。これまでの実践が立証しているように、資源の配置は大中都市と沿海地域に向かって傾斜し、自動車、高級分譲住宅の開発を通じて高額消費を刺激することで、短期間は依然として経済の急速な成長を維持することができる。しかし、人口の60%以上を占める人々を現代化のプロセスの外側に排斥する成長モデルは厚い基盤に欠けるものであり、長期にわたって続くことはむずかしい。その意味から言って、都市部と農村部の経済社会の発展を統一的に計画して、国民全体に現代化、経済グローバル化のもたらした収益を分かち与え、公平な問題を解決するだけでなく、長期の効率の問題を解決しなければならないのである。
第二、どのようにして政策を調整し、都市部と農村部の二元の経済構造を逐次変え、本当に都市部と農村部の経済社会の発展を統一的に計画するようにするか。大きな政策の調整(金融、財政、税収、土地制度、戸籍制度などを含む)をおこない、国民の収入分配構造を調整するかそれとも増加分の改革を強調するか。長期的政策に着眼するかそれとも短期の効果が現れる「便宜的な計画」を更に重視するか。
貯蓄の量を動かさず、利益の増加分の分配のルールだけを変えることは、既得の利益を手にしている人々の抵抗を減らすことができ、実施の面でわりに実行可能性があり、推進しやすい。例えば中央政府は、今後毎年教育・科学・文化・医療衛生などの事業経費を新規増加して、主に農村に用い、数年を堅持し、「小さなものも積もれば山となり」ということで、都市部と農村部における社会事業の発展の格差を逐次縮小することができ、これは大きな戦略的措置であり、長期的増加分の改革があることを決定づけるものだが、われわれもある度合いから言って、純粋な意義での増加分の改革がないことを理解すべきである。例えば温家宝総理は2003年3月18日の国内外の記者との会見の席で、今後の仕事の重要な方面は4項目の改革を推進することであり、第1の項目は農村での改革であり、農村での改革は農村の税収改革、食糧買付・販売体制改革、農民への補助方式の改革、農村金融体制の改革と農村医療制度の改革を含む。農業と農村経済の構造の戦略的調整は改革の深化と結び付けなければならず、いかなる改革措置もいずれもすでに存在する資源配置の状態を変え、それによって元の既得利益の構造に手をつけることになり、これに対してはっきりした認識をもつべきである。
第三、「WTO加盟」のチャレンジを迎え、経済の持続可能な成長を維持し、主に市場に頼るかそれとも主に政府に頼るか、ということ。
経済のグローバル化と中国の現代化のプロセスの中で、政府と市場のそれぞれの職能の位置付けの問題は終始経済発展のカギとなる問題である。政府は要素の自由な移動に役立ち、資源配置の最適化に役立つ市場環境をつくることに力を入れるべきであり、政府はくれぐれも企業の経済活動に直接参与しないかさまざまな行政手段、キャンペーンをくりひろげるやり方で企業あるいは農家の経営活動に関与してはいけない。WTO加盟後、農業と農村経済の構造の戦略的調整、農業産業化経営の発展および農村仲介組織の育成などは以前の痛ましい教訓を参考にすべきである。
農村の弱い立場に置かれた人びとが市場競争の中で不利な地位にあるため、政府の傾斜の政策とサポートは重要な役割を果たすことになるが、同時に非政府組織、コミュニティー、農民の協同組合および協会などが大きく発展をとげ、この部分の人びとの社会資本と組織の資本の地位を高めなければならない。
第四、農民の収入の増加は「足し算」(たくさん与える)をとるかそれとも「引き算」(少なく取る)をとるか。
両方から同時に仕事を進めるならば、もちろん最も理想的である。しかし、資源が限られている状況の下で、「引き算」の方が「足し算」よりも往々にして農民により多くの実益をもたらすことができる。2002年における農民の一人当たりの税負担は78.7元で、1997年より29.3元減った。2002年における農村住民の一人当たり消費支出は1834.3元で、昨年より実質5.8%増えた。しかし、消費支出の中のかなりの部分は剛性なしかたのない支出であり、例えば農民が出稼ぎに行くための交通費の支出と農民の子女が学校へ行くための授業料と雑費の支出がそれである。緑書のデータによると、2002年における農民の交通費と通信手段の一人当たり支出は128.5元で、昨年より18.1%増え、農民の生活消費支出の中でも増幅が最も大きな項目である。文化教育・レジャー娯楽用品およびサービスに用いられる農民の一人当たり支出は210.3元で、昨年より17.7元増え、9.2%伸びた。そのうち、授業料と雑費の一人当たり支出は160.1元で、昨年より14.9元増え、10.2%伸びた。授業料と雑費の増加額は農民の生活消費支出増加額の16%を占めた。資金投入あるいは補助金を増加し、さまざまな段階でそれを他の用途に使うようなことでは、農民特に最も大きな困難を抱えている農民は実益を手にしにくい。農業税、農業特産税を減免し、農民の子女の授業料と雑費を減免して、農民はすぐ節約した支払い分を持って消費し、物的資本と人的資本への投資を行い、それによって内需を始動させ、生産を発展させるのである。
第五、どのようにして農民の政治、経済、文化の権益(民主的権益)を保障するか、末端の弱い立場にある人びとはどのようにして憲法によって与えられた民主的権利を実行するのか、農村の管理構造の改革の方向は何か。
社会の発展は経済の発展であるだけでなく、更には社会の公平と社会の秩序を生まれ変わらせる問題でもある。「3農」問題を解決するには、改革を堅持し、深化させなければならず、まず深化しなければならないのは政治体制の改革であり、鄧小平氏は1986年に「経済体制改革だけを進め、政治体制改革を進めないならば、経済体制改革もやり通すことはできない。まず人の障害にぶつかるからである」と指摘した。この角度から言えば、われわれのすべての改革が最終的に成功するかどうかは、また政治体制の改革によって決定されるものである。村民の自治、税収改革と密接にかかわりのある県郷の機構改革、農民の自分たちの生産経営組織の育成などは、経済と社会の問題だけでなく、それらの成敗は同様に政治体制改革の方向と度合いによって決まるのである。(「チャイナネット」より)2003/4/15
|