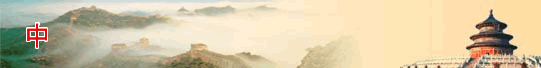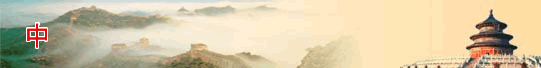|
河南省キョウ義市の黄冶村にある唐三彩の窯跡から唐代の青花(染め付け)磁器の破片や青花に近い「蘭彩白磁」が出土した。専門家は、黄冶村が唐代に青花磁器の産地であった可能性が極めて高いと推測する。唐代の青花磁器はこれまで江蘇省の揚州で見つかっているが、いずれも海外に流出し、わずか5点しか残っていない。
6カ所ある窯跡で集められた青花磁器の破片、唐三彩や素焼きの器の残片は1500袋余り、完全な形または復元可能な器物は約800点。白釉や黒釉、黄釉、青釉の磁器が完全な形で発見されたほか、大量に出土した優美な三彩の器や半完成品、各種の窯道具などは唐三彩の制作工程を示すものとして、黄冶窯の時期区分や作業場の配置、窯全体の構造などを研究するうえで貴重な資料となる。
発掘現場の地層はかなり厚く4メートル前後、最深で6メートルを超すため、完全な状態で出土したものが多い。最も注目を集めたのが青花磁器の破片と彩釉磁器だが、試掘した唐代の地層などから碗や杯、円筒状の器などの青花磁器が数点見つかった。釉色は純粋で火加減はやや高く、世界的に非常に珍しい。
河南省文物考古研究所の孫新民所長は「80年代初め、考古学専門家が揚州で出土した青花磁器を分析し、黄冶窯で焼成された可能性があると推断したが、当時はまだ黄冶窯では発見されていなかった。今回の出土はそれを実証するに足るものだ。また青花は唐代のものか、または宋代のものかを巡って学術界に論争があったが、中国陶磁器史のこの一大懸案も解決される期待が出てきた」と話す。
(「チャイナネット」より) 2003年5月8日
|