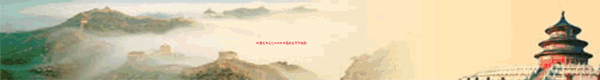|
最新の経済運営データによると、上半期の経済成長率は9.7%と同期比で8年ぶりに記録を更新し、同時に過熱気味だった投資もほぼ抑制され、農業生産と農民の収入増にも重要な転機が訪れた。経済の健全な成長はマクロ調整が時宜にかない、正確で実効性のあるものだったことを十分証明している。
今回のマクロ調整を1993年と比べると、根本的な相違は、当時は経済全体が過熱し、投資と消費の双方が高い伸びを見せ、インフラが深刻だったが、今回は投資が熱を帯びてはいるが消費はむしろ冷めており、インフラは起きておらず、経済運営では局部的に過熱していたことだ。
2003年初め、経済が急成長すると同時に、一部の業界や地区で盲目的な投資、信用融資の急激な増大の兆しが現われた。高すぎる投資の伸びが融資を引っ張り、原材料価格の上昇を招いてインフラ圧力が高まるとともに、石炭・電力・石油不足がもたらされた。
専門家は「中国経済が毎回大きく浮き沈むのは、速すぎる投資の伸びと無縁ではない。そのまま成長を維持させていれば、一旦、市場にニーズに変化が生じた場合に企業の生産・経営が困難に遭遇するのは必至であり、銀行の不良債権は増大し、一時帰休者・失業者が増加して経済運営と社会の安定に影響をおよぼす。事前の備えをし、時宜を逸することなく措置を講じて災いを未然に防ぐ必要がある」と指摘する。
アジア開発銀行中国代表事務所の高級エコノミスト・荘健氏は「今回の中国政府によるマクロ調整強化措置は、過去数回の調整に比べると顕著な違いがある。問題を早く発見して時宜を逃すことなく措置を講じたこと、市場を総合的に運用したこと、法律や行政など様々な手段を用いたことだ」と分析している。
今回のマクロ調整を仔細に分析すれば分かるように、経済全体が過熱していて「全面的に緊縮」せざるを得なかった1993年と違って今回は、保護するものと圧縮するものとに分けて二者ともに力を入れる、という個別対処を実施したことだ。過熱業界による倍増の投資と生産に比べ、農業生産はこの数年来低迷を続け、農民の収入増は低位を徘徊し続けてきた。社会や衛生、教育、科学技術など公益事業への資金投入も不足していた。こうした問題が長期にわたって解決されなければ、都市部と農村部の調和の取れた発展、経済・社会の調和の取れた発展は実現できず、庶民が真に経済成長の恩恵を受けることもできない。中国共産党中央は今回のマクロ調整で「保護と圧縮」の方針を明確に打ち出し、農業生産と農民の増収、また経済・社会の各未整備の部分を重点的に支援してきた。「三農」(農業・農民・農村)への今年の中央財政予算支出は昨年に比べると300億元増えている。全国29の省などで穀物栽培農民に補助金を直接支給しており、資金総額は116億元に達して6億人の農民が恩恵を受けた。8つの省などで農業税が免除あるいは基本的に免除されたほか、他の省などでも農業税率がやや引き下げられた。
国が「三農」への支援を強化し、また穀物価格が上向き始めたことなどが複合的に作用して、上半期の農民1人平均現金収入は価格要素を除いた実質で10.9%増加し、伸び幅は前年比で8.4ポイント上昇した。これにより、1997年以来徘徊していた農民の収入は新たな局面を迎えた。
世界銀行中国代表事務所の首席エコノミスト・ディーパーカー氏は「中国政府は現在、資源を実効性がなくしかも浪費が深刻な項目から真に必要とする地方へのシフトを試みているところだ」と評価する。
経済には様々な重要な転機が訪れた。この数カ月の間、政府のマクロ調整強化措置が成果を上げ始めてきたことだ。上半期の国内総生産(GDP)は前年比で9.7%増加し、経済は依然として比較的速い成長を維持しており、マクロ調整によって経済に"急ブレーキ"は掛からなかった。過熱していた業界はほぼ正常を取り戻し、経済全体の過熱は回避された。融資の増加幅は著しく下降し、市場価格の上昇は制御可能な範囲内にあり、引き上げ傾向もやや弱まった。
「チャイナネット」 2004年7月22日
|