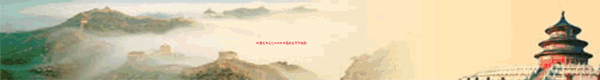|
中国教育部の張保慶副部長は8月31日の記者会見で、貧しい大学生への扶助貸付制度にはまだ問題があると認めながら、中国財政部、人民銀行、教育部などの機関が社会から広く意見を募った上で、この制度の実施システム、リスク回避の面ですでに調整を行ったと語った。
改革開放以来、中国の高等教育は飛躍的な発展を果たし、特に1999年に大学生募集枠の拡大策が実施されて以降、高等教育の規模には歴史的な突破が見られた。2003年末までの全国の大学在学生数は1200万人に達し、大学の進学率は19%まで引き上げられ、高等教育の大衆化は国際的にも認められるようになった。しかし、さまざまな原因で、大学生の中の貧困学生の比率も上昇しつづけている。調査によると、現在、貧困大学生はすでに在学生の20%を占める240万人に達している。
このような現状を踏まえ、奨学金、学生向けの貸し付け、アルバイト紹介、貧困手当て、学費の減免、学費納付期限の引き延ばしなど、一連の貧困大学生援助措置も打ち出された。これらの措置はかなりの役割を果たし、多くの貧困学生がざまざまな援助のおかげで学業を終えることができた。
1999年から始動された貧困大学生扶助貸付制度は、2004年6月末までに、すでに83万の大学生に52億元を貸し付けたと、張副部長が述べるとともに、この制度の問題点をも指摘した。1)地方と大学の責任者がこの事業を重要視していないこと。2)この政策の実行が徹底していないところもあること。3)調整して充実する必要もあること。4)援助経費の増加も急務となっていること。5)新たな援助方法の創出が期待されること。6)政策がより多くの人たちに知ってもらうため広報に力を入れること。
また、今後の仕事の重点について、張副部長は、現行政策の徹底、費用徴収制度の完備、むやみやたらな費用徴収の取り締りなどを挙げた。
「チャイナネット」 2004年9月1日
|