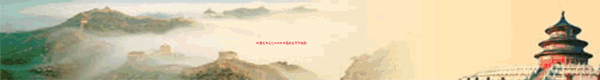|
中国国務院研究室副主任の江小涓氏は、9月18日の「2004年中国企業競争力年次総会」の席で、西側諸国の市場経済のルールから見ても、国内の市場経済の発展状況から見ても、中国はすでに「市場経済国」の条件を満たしていると強調した。
江小涓氏は、また、貿易摩擦の面で、一つの国に市場経済国としての要件がそろっているかどうかということでは、市場が資源の配置において十分に役割を果たしてるかどうかは基本的な基準にすぎない。そのほかにも行動の基準があり、つまり企業が競争の中で正しい行動を取っているかどうかがそれである。それと同時に、業績面の基準もあると述べている。
市場経済のルール及び基準について、江小涓氏は次のように述べている。市場経済国になるには3つの条件が要求される。1、消費財の価格が市場の需要と供給によって決められる。2.生産財の価格も市場の需給で決まる。3、異なる所有制の企業に平等な地位が与えられ、財産を処分する権利も同じである。前述の1と2の条件について、わが国では前世紀90年代にすでに解決済みで、中国政府の判断では1994年に解決したことになっており、中国の経済において、資源の配置は市場が中心的な役割を果たしている。3については、異なる所有制の企業間では、地位の平等、財産権の平等が進められたのは90年代後半以降だが、いまから見ると、この問題もすでに完全に解決されている。
企業行動の基準について、まず、企業の目標は、計画立案を実行し、利潤を追求することである。こういった目標は、1984年に中国で請負制度が実施されてからすでに確立されている。また、市場は生産財価格の変化に敏感に反応している。生産財の価格に大きな変化が生じたときに、企業は投入する生産財に対して、新たに組み換えをおこない、調整しなければならない。融資コストが上昇したときに、企業は資金の借り入れを減らし、労動力の合理的配置に取り組むべきである。国有企業は、この時代の変化の中で、90年代後半までは比較的に遅れていた。しかし、その後企業の予算は硬直なものから柔軟性のあるものとなり、これも市場の要請である。硬直した予算の下で、企業はいかなる目標があっても、資金面の支援を得られないことには、企業として淘汰される以外にない。企業の行動基準に関しては、すでに20年余り議論されており、現在の中国企業はすでに大きく改善されている。
企業の業績については、市場経済において、異なる産業の間に、利潤平均化の傾向がある。計画経済時代のときは、経済資源は政府によって、計画にもとづいて配置され、資源の異業種間の移動がなかったため、異なる産業間の利潤の差は著しかった。しかし、いまは状況が大きく変わった。江小涓氏は、特殊な産業を除けば1985年、利潤が103%以上達した産業は7つ、5%を上回った産業は16にのぼった。これは高利潤産業と低利潤産業間の生産要素の移動がなかったことを物語っている。しかし、1995年以降、状況は急速に改善し、利潤を10%以上達成した産業は皆無で、5%を上回った産業は5つだった。2002年になると、10%以上達成した産業は皆無で、5%を上回った産業は2つだった。これは、産業間の利潤が大きく変化するときに、投資主体の企業は参入と撤退の時期に敏感に反応していることの証左である。
したがって、中国はすでに市場経済国の基本的条件を満たしている。西側諸国の市場経済におけるルールだけではなく、企業の行動基準と業績の基準を加えて判断しても、中国は市場経済国の条件を完全に満たしていると江小涓氏は語っている。
「チャイナネット」 2004年9月23日
|