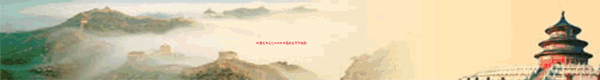英誌「ザ・エコノミスト」は、このほど、中国の経済発展についての論評を掲載した。それは、中国においては貧富の格差が拡大しつつあるものの、これは「発展過程の問題」で、克服することができる。実際は、中国沿岸地域の経済の繁栄はすでにだんだんと内陸部に浸透しているという内容のものだった。
論評は、過去20年余りにおいて、中国の改革開放に伴い、大量の労働力が西部から東部へ移動した。これは2つの結果をもたらし、1、人口の移動で、東部の急速な経済発展の成果がすぐに広大な内陸部に波及することになった。2、周知の中国の都市化プロセスである。国連のおおまかな統計によると、中国の都市人口の割合は過去25年間でほぼ倍となり、40%を上回るに至った。19世紀のアメリカは約50年かかり、中国の2倍の期間を費やして、やっと同様の発展を達成した。論評は、中国の都市化のスピードは世界で最も速いと言っても過言ではないと指摘している。
人口の移動に伴い、経済の発展も次第に内陸部に浸透している。「ザ・エコノミスト」誌のこの論評は、中国沿岸地域は内陸部に大きく波及効果を及ぼし、両者の間の境はすでに内陸部へ数百キロも後退した。この論評が有力なよりどころとしているのは、華東地域の上海が急速な発展をとげ、長江デルタ全体の経済を明るく照らしている。そして世界の巨大な製造基地を誇る広東省の経済発展の勢いも次第に千キロ以外の内陸部に波及していると見ている。
中国で先般打ち出された汎珠江デルタ「9プラス2」{福建省、江西省、湖南省、広東省、広西チワン族自治区、海南省、四川省、貴州省、雲南省などの9つの省・自治区とさらに香港と澳門(マカオ)特別行政区を加えた経済圏}地域協力では、香港と澳門(マカオ)をも引き込み、中国の1/3近くの人口をカバーするものとなった。論評は、長江デルタと珠江デルタの二つの大きな地域と上海、香港の二つの大きな「中核」のけん引によって、中国経済の発展は必ずや沿岸地域のみの独立した発展とは比べものにならないほどの繁栄をもたらすに違いないと分析している。
論評はさらに、上述の経済発展の勢いの波及効果によって、中国内陸部の立ち後れた地域も自らの過去と比べると常に前に進んでおり、したがって、貧富の格差が大きいという問題は「貧しい者がさらに貧しくなる」という状況よりは比較的に容易に克服することができると指摘している。統計データでは、中国の農民の収入は増え続けており、なお今年は初めて都市・鎮住民の収入の増加幅を上回り、10%増を実現したと、している。
論評の最後では、中国国内の消費・需要は中国の経済成長の力強いエンジンとなっており、ベトナムとインドからの競争があっても、中国は近い将来必ず世界中でコストの最も安い製造業基地となり、沿岸地域の経済の繁栄も必ず絶えず内陸部に広がっていくに違いないとしている。
「チャイナネット」 2004年12月1日
|