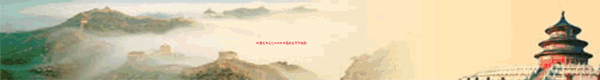中国は11日、世界貿易機関(WTO)加盟から3周年を迎える。WTO加盟交渉で中国側リーダーを務めた龍永図・元首席交渉代表(現博鰲〈ボアオ〉アジアフォーラム事務局長)はこのほど、WTO加盟後の3年間について、記者の質問に答えた。
――最近、一部の人々が、WTO加盟協議の一部「不利な条項」について疑問を投げかけ、これは加盟交渉で残った「しっぽ」であり、中国に不利な立場をもたらすおそれがあるとしている。これをどのように見るか。
いわゆる「不利な条項」とは、第15条(市場経済国としての地位に関する問題)と第16条(特別保護措置)にほかならない。現在、誤解があるようだが、実際の影響は非常に限定的なものだ。
市場経済国の地位を例に挙げると、協定書の規定では、(非市場経済国としての差別待遇を受ける企業は)国外でダンピング調査に遭った企業のみで、すべての国内企業に対する規定ではない。割合としては小さく、昨年反ダンピング調査を受けた中国製品は、輸出総額に占める輸出額の割合はわずか0.5%だった。また、「不利な条項」にも進歩した面がある。以前はダンピングがあると非市場経済国の待遇を受け、提訴された企業は「代替国」の価格水準を元に反ダンピング税を算出された結果、大きな損失を受けた。しかし第15条は中国企業にもう一つの可能性を与えている。つまり、調査を受けた製品の製造・生産・販売のプロセスが市場経済の条件に合致し、政府から補助金の支給を受けておらず、不当競争ではなく、帳簿に虚偽がないことを証明できれば、中国国内の価格・コスト水準による計算が認められる。これは、ダンピング調査を受けた国内企業にとっては一つの活路であり、過去3年間、成功したケースも少なくなかった。さらに、「不利な条項」は値下げ競争の抑制、業界の自律促進にもある程度効果がある。このため、2つの条項のマイナス面だけを誇張する必要はなく、全面的・歴史的・客観的に見なくてはならない。
「人民網日本語版」 2004年12月7日
|