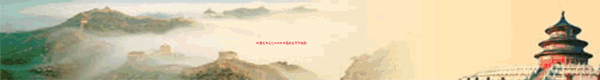中国は11日、世界貿易機関(WTO)加盟から3周年を迎える。WTO加盟交渉で中国側リーダーを務めた龍永図・元首席交渉代表(現博鰲〈ボアオ〉アジアフォーラム事務局長)はこのほど、WTO加盟後の3年間について、記者の質問に答えた。
――3年前と比べた中国の大きな変化は、どのようなものか。WTO加盟は改革開放のプロセスに対して促進作用があったか。
この3年間、WTOフィーバーが全国に広がるにつれ、市場経済の基本原則や理念も、人々の心に根づきつつある。例えば「国民待遇」(あらゆる出資形態の企業に同じ待遇を与えること)について、WTO加盟の前に注目されていたのは外資系企業に対する待遇の問題だったが、WTO加盟後には問題に対する認識が広がり、国内企業に対する差別的待遇の撤廃も求められるようになった。特に、数多くの民間企業が平等競争のチャンスを持てるようになったことは、大きな進歩だといえる。
透明性については、外資系企業の経営者が以前、「中国投資で恐いのは、優遇政策を受けられないことより、むしろ不透明なことだ」と話している。中国はこの3年間、貿易や投資、関連政策における透明性が大幅に改善している。特にWTO加盟後は、政府部門による取り組みが効果を上げ、各地方政府は争って透明性の高い「陽光政府」の構築を進めている。行政管理制度・法律制度の規範化や整備が進んだ結果、提携先の信頼感も強化された。中国はこの3年間、対外輸出で30%、外資導入で40%の増加率を保ち、今年の貿易額は3年前の約2倍に当たる1兆ドルの大台を初めて突破する見通しだ。外資導入額は初の600億ドル超の見込み。これらがすべてWTO加盟の効果とはいえないが、WTO加盟が重要な要因であることは疑いない。
指摘すべき点として、中国はWTO加盟後、WTOのルールを機械的に実行したわけではない。協定にある内容だけを問題にするのはおざなりな態度に過ぎず、社会全体に深い影響を生み出すことはできない。中国によるWTOの承諾事項の実行プロセスでは、WTO効果を単なる貿易政策だけでなく、より広い、より深い分野に浸透させることで、開放による改革・発展の促進という目的を達成できた。
「人民網日本語版」 2004年12月7日
|