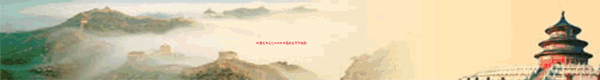中国は11日、世界貿易機関(WTO)加盟から3周年を迎える。WTO加盟交渉で中国側リーダーを務めた龍永図・元首席交渉代表(現博鰲〈ボアオ〉アジアフォーラム事務局長)はこのほど、WTO加盟後の3年間について、記者の質問に答えた。
――2005年をめどとして、中国の主要産業はWTO加盟交渉の中で「保護」、「調整」、「延期」、「漸進」という言葉で表される過渡期にピリオドを打った。今後の数年をどのように見るか。その中で最大の試練とは何だろうか。
まず一つ訂正しておきたい。最近、2004〜2005年をWTO加盟の「ポスト過渡期」と呼ぶ人が後を絶たないが、正しくは一部業界がWTO加盟協定の実行における「ポスト過渡期」に差し掛かったと言うべきだ。例えば銀行や基礎通信など。他の大多数の業界はすでに過渡期が完全に終わっている。また、過渡期とは一つの段階に過ぎず、その終了は開放プロセスの完了を示すわけではなく、国内の開放の程度が最高レベルに達したことを示すわけでもない。われわれにとっての開放とは、承諾事項の実行のための開放であるほか、結局は自身の利益のための開放である。現在、中国の一部分野における開放レベルは一部発展途上国にも追いつかない。
開放はさらに拡大するべきであり、今後数年間の実際の開放は、議定書の中で合意した水準を超えなくてはならない。
現状から見ると、WTO加盟は一部の敏感な分野に対しても大きな衝撃にはなっておらず、過渡期中には国内産業の競争力が大幅に強まった。しかし、はっきり認識すべき点として、一部の重要な産業や、国家経済や国民生活に関わる産業は、今後の試練が大きくなると見られる。最大の試練は国際競争の長期性や、困難に対する認識?準備の不足だ。以前から言う通り、「開放は恐くない。恐いのは準備不足だ」といえる。
――今後一定の期間において、国内のWTO加盟への対応策や対策措置に対してどのような調整を行うべきか。
全国での貿易政策の統一的な実施、知的財産権保護などの面を適切に強化する必要がある。繊維品や農産品の問題にもWTOルールを適用する必要がある。例えば、来年1月1日に全世界で繊維品の輸入割当制限が撤廃される予定だが、これにより国内企業が何の制限も受けなくなるわけではない。われわれは貿易国としては3番目の規模で、競争の中で他の発展途上国の輸出の利益や、輸入国側の市場の負担能力を考慮し、産業の自律をしっかりと保たなくてはならない。
20年以上にわたる改革開放、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)への復帰やWTO加盟への15年間の努力を経た発展途上大国として、われわれは絶えず進む経済のグローバル化という新情勢に合わせ、WTOでの協議の中で利益共有の模索に努力する必要がある。
「人民網日本語版」 2004年12月7日
|