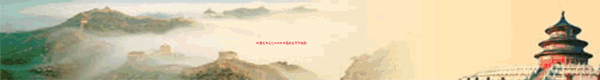|
▼中国社会科学院日本政治研究室・王屏副主任
2004年、中日関係は膠着状態の中にあって転機を醸成しつつあった。中国の対外関係の中で、中日関係はある種最も「ねじれた」2国間関係である。「一衣帯水」の近隣関係、互いに似通った文化的根源、緊密に結びついた経済交流、恩讐に満ちた歴史的衝突が、中日両国の相互交流において、理性的認識よりも感情的認識が上回る結果を招いている。この点を理解すればこそ、2004年、中国政府・メディア・学界はいずれも「民意」を理性的方向へ導くべく努力したのである。しかし、関係改善には双方の共同努力が必要である。日本の小泉純一郎首相による元旦の靖国神社参拝は、2004年全体の中日関係に暗い影を落とした。中日関係は苦難の中で歩みを緩めている。
2004年の中日関係には、次のような特徴があった。
(1)両国ともに、関係改善を希望
中日間にはさまざまな新旧の摩擦と利害衝突が存在するが、両国政府の関係機関と民間は、いずれもたゆまず努力し、戦略的角度から両国の歴史問題および突発事件を認識および処理するよう試み、全力で利益の一致点を模索している。
(2)両国ともに、新たな対話・交流形式を模索
中国の新世代の指導者は対日外交の実践の中で、独自の姿勢を形成した。つまり「言うべき事は率直に言う」ということだ。率直で実務的な対日外交姿勢は、中国首脳の外交的透明度を高めるとともに、厄介な中日関係の改善に向けて新たな交流形式を見出すことになった。
(3)両国ともに、協力の強化が自国の核心的利益に合致すると同時に、地域政治・経済安保などでの調和的発展を促すことを理解
地域協力の強化と東アジア共同体の建設は、現在東アジア各国が積極的に追求している目標だ。中日両国が歩調を合わせて発展できないなら、東アジアの地域協力という大きな目標の実現だけでなく、中日両国の民族的利益にも影響を及ぼすことになるだろう。これまでの経験は、両国がともに戦略的角度から中日関係に配慮し処理すれば、複雑な情勢を前に受動的立場から自発的立場へと変われることを証明している。
「人民網日本語版」 2004年12月24日
|