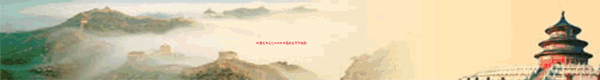|
伝えられるところによると、イラクでこのほど武装勢力によって拉致され、その後解放された中国人8人が、無事福建省の故郷に戻った。
これは昨年8月に続き、福建省平潭県の農民労働者が海外で窮境に追いつめられた件としては2回目となったため、国内の人々の幅広い関心を呼んでおり、いかにして農民労働者の労務輸出管理を改善するかということが注目を浴びるようになった。
福建省師範大学産業経済研究センターの郭鉄民主任は、福建省は国内の主な海外労務輸出省である。人質事件は沿岸部の労務輸出管理の不備を顕在化させ、政府は全面的に農民労働者就労の道を開拓する面で考え直すことが迫られていると指摘している。
中国の対外労務協力事業は 1979年に始まって以来急速な発展を遂げ、2004年4月末までに、対外労務協力はすでに売上高が合計280.7億ドルに達し、さまざまな労務人員合計301.4万人を派遣した。しかし、そのうちかなりの部分は地元の人たちあるいは知人を通じるか、さらには不法な仲介業者のあっせんで出国したため、海外で就業できず、生活が行き詰まり、合法的な資格がないなどで苦しい立場に置かれるなどを経験した人が数多くいる。
郭鉄民主任は、農民たちが命の危険を冒してでもイラクなどの国に就労に行くことは一時的な衝動ではなく、「利益のため」であると指摘している。そのため、農民たちが自分の就業目標に対して理性的に、客観的に考えるよう手助けをし、各クラスの人民政府と関係部門は農村余剰労働力資源の開発及びその効率的な利用の面でさらに具体的で多方面にわたる努力を行うべきだと、郭鉄民主任は語っている。
専門家たちの農民労働者の収入の変化に対する追跡調査結果によると、過去10年間に、沿岸部とりわけ福建省、広東省などの地域の農民労働者の収入は大体毎月500−800元のレベルにあるが、イラク、イスラエルなどの国に就労に行く場合、毎月4000−6000元の高給を約束する労働者募集広告も目に付く。
日増しに拡大しつつある農民労働者労務輸出市場に対して、中国国務院は2000年に『出入国仲介業務の管理強化に関する通達』を公布し、さらに2002年には『海外就労仲介管理協定』を公布したが、なお一部の不法仲介業者は農民たちの豊かになりたいという心理につけこんで不法な仲介を行っている。
これに対し、郭鉄民主任は、かりに最も末端の郷・鎮所属の機関が農民たちに対して、全面的な職業技能トレーニングや研修教育を行い、この人たちがタイムリーに中国外交部の出国に関する通達などの情報の入手に協力していけば、事情はいくらか好転することになろうと語っている。
「チャイナネット」 2005年2月1日
|