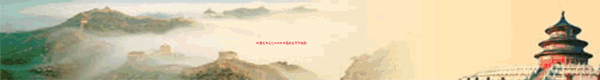|
アメリカの首都ワシントンの環境保護シンクタンク地球政策研究所が近日公表した調査レポートの中で、アメリカの著名な社会学者――地球政策研究所所長のレスター・ブラウン博士は、中国の1人当たりの消費量は依然としてアメリカよりはるかに低いが、食糧、肉類、鉄鋼、石油と石炭の5種類の主要な消費財において、中国はアメリカを追い越し、世界最大の消費国になりつつあるという見方を示した。
まず食糧と肉類を見ると、2004年の中国の食糧消費総量は3.82億トン、アメリカは2.78億トンであった。中国の13億の人口が6400万トンの肉類消費したが、アメリカの約3億の人口は3800万トンだけを消費した。
次に鉄鋼と石炭を見ると、中国の2004年の鋼材消費量は2.58億トンで、アメリカと日本の消費量の合計に相当する。中国の石炭消費総量は8億トンで、アメリカの5.74億トンのレベルをはるかに上回る。
最後に石油であるが、5種類の基本的資源の面で、石油消費だけはアメリカが絶対的優位を示し、1日あたりの石油消費量は2000万バレルで、中国はアメリカの1/3にとどまっている。しかし、同レポートでは、中国の石油消費の潜在力は驚異的であると指摘している。過去10年におけるアメリカの石油消費量はわずか15%増であったが、中国の伸び幅は100%を上回った。このスピードで発展すると、中国の石油消費量がアメリカに追いつくのは時間の問題であるとしている。
同レポートはまた、中国の消費財市場の規模の大きさは、中国人の保有する電気冷蔵庫の量がすでにアメリカを超え、テレビの保有台数がアメリカに比べると50%多く、携帯電話は更に66%も多いなどに現われていると指摘している。
レスター・ブラウン博士はさらに、中国が徐々にアメリカを追い越して世界最大の消費国になることは、中国が発展して新しい経済超大国になることを意味する。中国が世界の原材料消費の中心になるにつれ、中国の国際政治に対する影響力も変化しつつある。中国は原材料やエネルギー供給国(例えばブラジル、カナダなど)と戦略的関係を結び、国際政治が次第に多極化に向かうことを促す役割を果たせるようになるとしている。
「チャイナネット」 2005年3月1日
|