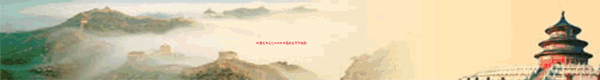|
現在、「調和のとれた社会」を構築するということが社会世論のホットな話題となっており、目下開催中の「両大会」においても人民代表や政治協商会議の委員たちの注目を浴びている。「調和のとれた社会」とはいったいどんな社会なのか、このような社会をどういうふうに構築するのかをめぐって、「チャイナネット」の記者はこのほど社会学者の李培林博士にインタビューした。
「チャイナネット」:昨年の中国共産党第16期4中全会の決議で初めて「調和のとれた社会」を提起されたが、執政党として、現在の社会条件の下で調和のとれた社会の構築を打ち出したのはどういう考えからなのでしょうか。
李:これは発展の必然のなりゆきです。中国は改革開放政策を実施してすでに26年が経ちました。この26年間に経済体制と社会構造には急速な転型が見られ、その大きな成果は世界の注目を浴びている。これほど短期間で、これほど多くの人口を擁する国と地域的規模でこれほどの変化を遂げたのは現代世界史上においてもまれに見るものでしょう。こうした発展に伴って、収入格差の拡大、都市部と農村部の発展のアンバランス、就職問題の顕在化、裕福になる前に現れた人口の高齢化、ゆゆしい環境汚染など、社会的諸問題が現れてきました。これらの問題について、これはいずれも「貧困」から生じた問題で、経済の発展と富の急速な蓄積につれて自然に緩和または解決できると、もともと私たちは考えていたが、これら問題の変化の法則について追跡調査と観測を行った結果、多くのものは経済の発展と市場体制の完備の過程で自然に解決できるものではない、ということに気づきました。したがって、私たちは科学的発展観を導きとして、高成長で調和のとれた発展を目指すルートを探し出すべきであると思います…。
「チャイナネット」:李さんはいろいろなところで現段階は中国の経済社会の発展における「肝じんかなめの時期」であると言われていますが、この「肝じんかなめの時期」とは何を指すものでしょうか、どうしてこの時期に社会の調和に気を配らなければならないのでしょうか。
李:我が国の社会経済の発展はここ10数年に最適の時期に入りました。2004年の国内総生産(GDP)は9.5%の伸び率となり、物価指数と住民消費価格の上昇は約3%で、都市部の失業率には1991年以来最初の低下が見られ、農民の収入は長年らいかつてない大幅な伸びを遂げました。これと同時に、中国の発展も一人当たりのGDPは1000㌦から3000㌦へ伸びるという転型の肝じんかなめの時期に入ったのです。他国の経験から見れば、この時期は往々にして、産業構造が急速に転型し、社会利益の分配の枠組みにも激しい変化が起こり、政治体制も続々と新しいチャレンジに対応し、さまざまなチャンスと社会的リスクに直面する時期となります。世界の一部の国と地域は1970年代の高度成長を経て、この時期に入りましたが、その後はまったく異なる発展の道を歩んでいます。順調な発展を遂げた国の一人当たりのGDPはすでに1万ないし2万㌦に達しているが、発展途上の矛盾や問題を上手に解決できなかった国のGDPはまだ4000㌦未満の程度にとどまっています。ですから、現段階の肝じんかなめの時期において、社会の基本的な利益関係に特に注意を払い、発展を阻害するさまざまな社会問題を解決し、調和のとれた社会を構築することによって、10数億の人たちに恵みをもたらすことのできる改革開放と経済社会を発展させる偉大な事業の中でさらに大きな成果をもたらすことができるだろう。
「チャイナネット」:調和のとれた社会はどんな特色、またはメルクマールを備えたものでしょうか。
李:まずは相対的に裕福な社会です。調和のとれた社会は豊富な物質的富の基盤を必要としており、貧困は社会主義ではないと言われているように、貧困社会は調和のとれたものではありえないのです。けれども、裕福だけでもだめで、財産の分配と利益の協調がどうなっているかも見なければなりません。この意味から言えば、調和のとれた社会には基本的な公平と正義を確保し、人々が成長と発展のメリットを分かち合えるようにしなければなりません。
その次に、調和のとれた社会は安定かつ秩序のある社会です。しかし、安定と秩序だけでは必ずしも調和のとれた社会とは言えません。安定と秩序の上にさらに活力があることです。あらゆる労働、知識、技術、管理と資本のパワーがほとばしり出て、社会の富を創造できる「源泉」が充分にその役割を果せることです。第三に、調和のとれた社会は利益面の調和だけではなく、価値の面の調和をも含むものです。調和のとれた社会では、人々がその居に安じてその仕事を楽しみ、事業に成功し、心地よい社会状態であることはもちろんのことで、比較的強い公民意識と良好な公民モラルも必要で、人々が心を一つにすることに役立つ、未来志向の社会主義の価値体系とイデオロギーの形成が必要です。グローバル化が進む世代の交代の中で、価値観の融合感は中国にとってますます重要になってきていると思います。
「チャイナネット」:具体的には、どの面の調和を意味しているのでしょうか。
李:一、都市と農村の構造のバランス。現代化国のメルクマールとなる指標は農民は貧困者ではないことです。しかし、我が国の現状は、都市と農村における収入と福祉の格差が開き過ぎており、この格差は国内市場の発展にも影響を及ぼしています。世界の基準で計算すれば、我が国の農村には比較的に多くの低収入層と貧困者が存在しています。ですから、新世紀においては貧困減少プロジェクトを実施し、農村で社会保障の基本的な枠組みを構築すべきです。
二、地域的な構造の調和の形成。中国では地域的発展と収入の格差がまだ拡大しつつあります。私たちは、東部の急速な発展、西部大開発、東北地域の旧工業基地の振興、中部の勃興と言った地域発展の新しい枠組みを構築する過程で、この格差拡大の趨勢を逐次転換していかなければなりません。
三、社会階層構造の調和。貧富格差の拡大の加速はそれぞれの社会層相互間の利益の摩擦と衝突を招き、時には激しい衝突となることもあります。新しい情勢の下での人民内部の矛盾、特に貧富の関係、労働争議、官民関係を上手に処理しなければなりません。政府は財政、税収、福祉などのテコを利用して、収入の再分配を科学的に調整し、中程度の収入の人たちを増やし、貧困層と低収入層を減らし、さらに幸福、公正、調和の取れた、節約で活力に富む社会を構築すべきです。
四、就職構造の調和。我が国では現在、農業生産に従事している人口は49%に達しています。これは現代的な社会構造への転型を完成するうえでの障害となっています。これを解決するため、向こう15年間に1億以上の農村労働力を都市部に移転させる努力が必要で、さらに多くの就職の機会を創出し、職業訓練や教育を発展させ、人口大国を人的資源の大国に変えなければなりません。これは経済の高度成長を維持するうえでの重要な一環です。
五、人口の世代構造の調和。我が国は30年間にわたって計画出産(家族計画)政策を実施することにより、年平均の純増加人口は約800万に低下しましたが、すでに裕福になった一部の国と異なり、我が国はまだ裕福にならないうちに人口構造の先取りした老化が現れることになりました。そのため、節約を重視し、カバー率が高く、蓄積のある持続可能の社会保障制度を確立し、価値観についての世代間の認識の整合が必要となっています。
このほか、13億の人口をかかえる大国として、持続可能な成長を保つには、人間と自然の間の調和をとることに意を配らなければなりません。資源節約型の生産と生活方式を確立し、脆弱な生態系を保全しなければなりません。グローバル化の新しい情勢の下で、権利意識の成長を高度に重視し、社会主義民主制度の完備を通じて、腐敗現象を抑制すると同時に、管理の社会的技術レベルを高め、政治の長期安定を確保しなければなりません。中国は一大国として、国際的地位を高めると同時に、冷静な政治的頭脳を保ち、国際関係を上手に処理し、特に隣国間の関係、大国間の関係を重要視し、我が国の長期的に安定した発展のために、できるだけ有利な国際環境を作りだすべきです。
「チャイナネット」:ご承知のとおり、各方面の関係を上手に協調させることは「調和のとれた社会」を構築するうえでの前提です。それを達成するために、政府はどんな役割を果すべきでしょうか。
李:収入分配の合理化、社会保障制度の完備、社会矛盾の適切な処理、就職機会の創出、社会公平の擁護、社会リスクの予防などを目標としたマクロ調整メカニズムの構築など、この面の仕事は非常に多いと思います。重要なのは、社会構造の変化につれて、管理方式もそれに伴って変化していくことを認識しなければなりません。実践を通して、現段階では政府と市場の関係は上手に協調することができるようになっていますが、これからの実践の中で、新しい条件下の政府と社会の関係を上手に協調させなければなりません。
「チャイナネット」:調和のとれた社会を構築し、政策と計画をさらに弾力性と柔軟性をもつようにすることは、政府にとって必要でしょうか。
李:改革の深化に伴い、すべての人にメリットをもたらすような改革措置はほぼ存在しなくなっていきます。しかし、社会においては競争中の弱者を扶助するメカニズムが必要です。政策や計画は、もとろん新たな変化、新たに現れてくる社会問題に対応して調整を行わなければなりません。すべての人を満足させる絶対の社会的な公平は存在しませんが、社会が基本的に認知できる公平な法律と制度は確立しなければなりません。
(李培林博士:1955年山東省の生まれ、1987年フランスのパリ第一大学で社会学博士を取得。1993年から中国社会科学院社会学研究所副所長の任にある。)
「チャイナネット」2005/03/11
|