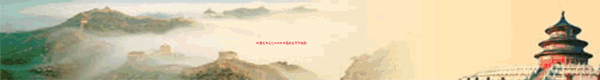|
今年2月以降、米軍高官から「中国の軍事的脅威」の発言が後を絶たない。発言は「中国軍の近代化は台湾海峡両岸のバランスを破り、周辺地域に駐留する米軍への脅威となり得る」「中国は絶えず軍事費を増やしている。中国海軍は潜水艦能力を徐々に高めている。今後10年以内に中国海軍の規模は米国を上回るかもしれない」などだ。米日両国は欧州連合(EU)による対中武器禁輸措置の解除に全力で反対している。その理由もまた「中国の軍事的脅威」論だ。
中国は、国土防衛の必要性と世界の新しい軍事技術革命の流れに適応するため、軍事力の増強をここ数年一定程度進めている。しかし米国や日本と比べて、その隔たりは依然として大きくかけ離れている。
軍事費の支出を見てみると、米国の2004年度国防予算は4013億ドルで、さらにイラク戦争とアフガニスタンへの対テロ戦争で870億ドルを追加補正した結果、総額は4883億ドルに達し、全世界の軍事費支出総額の半分を上回っている。日本の2004年度国防予算は422億ドルだ。中国は2117億元(約255億ドル)。中国の国防費は米国のわずか5.2%、日本の60.4%に相当する。中国の人口1人当たり国防費はおよそ20ドルで、米国の人口1人当たり支出のわずか77分の1しか占めていない。
兵員数で見てみると、米軍は予備役と文官を含めて約300万人。中国軍は今年の人員削減後で230万人だ。
海軍力で見てみると、米軍は11の航空母艦群を持っている。中国軍はいまだに排水量8000トンを超える大規模な軍艦を1隻も持っていない。中国海軍の目的は領海防衛で、米軍の目的は他地域に軍事力を投入することだ。
海外駐留軍を見てみると、米軍は130余の国・地域に駐留しており、海外に軍事基地を数百カ所持っている。中国軍は海外に一兵卒も駐留していない。
軍事技術システムを見てみると、米軍は成熟した機械化を実現しており、情報化への転換もほぼ終えた。中国軍の機械化の道はゴールまではるか遠く、情報化整備はよちよち歩きを始めたばかりだ。昨年の米国のあるレポートにおける推計によると、中米両国間にはおよそ20年ほどの軍事技術の「時代格差」があるという。
以上のようなデータを見てみると、中国が米日に対して軍事的脅威になるなどと誰が信じられるだろうか。
ある国が本当に他国に対して軍事的脅威になるのかを判断するには、その国が実際において最終的にどんな性質の軍事戦略と国防政策を遂行するかを見なければならない。新中国は成立以来、一貫して積極的な防衛的軍事戦略と防衛的国防政策を堅持してきた。中国は一貫して核兵器を先制使用しない政策を遂行し、核軍備競争に参加せず、国外に核兵器を配備しないできた。それに対して、米国は「最良の防衛は攻撃こそ有効である」との戦略理念に則って、「先んずれば人を制す」原則に基づく積極的な先制攻撃戦略を強調する。米国はまた核による威圧と抑止の戦略を積極的かつ能動的に遂行し、核攻撃目標を核保有国から非核保有国へ広げようとしている。
「中国の軍事的脅威」論が重要な「根拠」となるのは台湾問題である。台湾問題は中国の統一事業にかかわることであり、中国には自ら国土内で軍事力を調整する権力がある。米国がこれにやたらと批評、指図する理由はない。
中米両国はいずれも現在の世界の全局面を左右する大国である。仲良くすることは双方に利益があり、争うと双方が傷つく。中米両国は戦略的視点と長期的視野から両国関係の不協和音を見つめ、把握しなければならない。そうすることでようやく、それぞれの国家利益を確保、実現でき、地域の安定と世界の平和を共に促進できるのだ。
「人民網日本語版」2005年3月24日
|