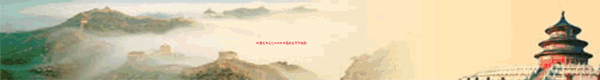|
我が国経済の健全かつ持続的な発展と農村住民の収入の絶え間ない増加につれて、住民の消費水準を示すエンゲル係数には低下の趨勢が表れ、そのうち浙江、江蘇、山東など東部地区の農民は「温飽型(衣食の問題を解決したばかりの状態)」から「小康(ややゆとりのある状態)」への転換をなしとげた。
商務部のある調査レポートは、農民に優遇を与える中央の諸政策の実施で、農民の収入は急速に増加し、消費水準もそれ相応に向上しており、2004年における山東、江蘇、浙江三省の農民の収入はそれぞれ3642元、4754元、6069元に達し、1998年に国が内需拡大の戦略を確立した時に比べるとそれぞれ48.5%、40.8%、59.8%増加し、三省農民の平均消費は3000元を上回り、そのうち浙江省農民の消費支出は4600元を超え、江蘇、浙江の一部地域の農民はすでに裕福型の段階に入っていることを明らかにしている。
調査レポートはまた、農村における生活必需品の消費支出は明らかに下がり、生活の質を向上させる通信、娯楽、医療、交通などの支出が著しく増えた。現在、三省の農民家庭のテレビ、携帯電話、コンピュータ、自家用車の保有率はそれぞれ50%、35%、3.1%、2.6%を上回り、コンピュータ、携帯電話、乗用車を買おうとしている農民はそれぞれ11.5%、7.8%、7.3%に達している。
レポートの作成に参加した関係筋によると、食品の消費においては、これら地域の農民は食品の安全と栄養を重視するようになっている。多くのスーパーでは、パック牛乳が粉ミルクを上回って、重点取扱い商品となり、一部のスーパーでは、パック牛乳がその店の売上の重要な構成部分となっている、という。
7.7億の人口を擁する農村市場は巨大な消費市場となりつつである。国家統計局の推算によると、農村人口の消費支出が1元増えるごとに、国民経済に2元の消費ニーズをもたらし、農村人口の間でいかなる家電製品の普及率が1%伸びれば、238万台の消費ニーズが増えることとなる。農村消費市場を牽引することはすでに内需拡大の重要な内容となっている。
「チャイナネット」2005/07/28
|