六百人の「捨て子」に捧げた愛
文・写真 鄧勃
 |
花柄のスカーフを深々と被った村の女が、涙を拭いながら石畳の路地裏を歩いてきた。女はとある人家の前で足を止め、胸に抱えていた段ボール箱をそっと下ろした。古びた木の扉をトントンとノックすると、女は決心したかのように踵をかえして闇の中に消え去った。
ドアが開き、女主人・労秀玉さん(56)の顔がのぞいた。ほの暗い明かりが段ボール箱を照らす。その中には、弱々しく青白い顔をした嬰児が背中を丸めてふるえていた。労さんは急いで赤ちゃんを抱き上げ、後を追って出てきた男の子にため息をついた。「弯児、あんたのようなかわいそうな子が、また捨てられたんだよ」。労さんは、何とかこの幼い命を救おうと手を尽くしたが、不幸にも赤ちゃんは数日後に息絶えたのだった――。
広東省雷城鎮(町)に、労秀玉さんを訪ねた記者は、ちょうどこの不幸な一部始終に立ち会った。「及ばずながら、母親代わりにできることをしてあげました。赤ちゃんがあの世で安らかに眠るよう祈るだけです」。弯児を抱き寄せながら話す労さんの目に涙が浮かぶ。「この20年間、実に600人近い虚弱児を引き取ったけれど、捨てられた時にはもう手遅れの状態。わずかだけしか助かりませんでした。そのうち体が不自由な子で元気に育ったのは弯児一人だけなんです」
 |
 |
4年前のある寒い朝、次女が玄関の前に捨てられた男の赤ちゃんを発見した。弱々しく痩せ細り、腰は曲がって手足も不自由。もう助かりそうにはなかったが、労さんはあきらめなかった。さっそく抱き抱えて温かいベッドに入れ、必死になって手当をした。厚い介護の甲斐もあり、赤ちゃんはついに息を吹き替えした。哀れみと慈愛の情を抱いて、彼女はこの子に「弯児」と名を付けた。腰をぴんと伸ばすため、暇さえあれば自分の手の上に彼を仰向けに載せて、上下に振る運動をした。そうして四年の月日が流れた。弯児の腰はだんだんとまっすぐになり、手足の形も正常に戻ってきた。今度は彼の手をとっての歩行練習だ。はじめは壁際の水道管につかまり、少しずつしか進めなかったが、やがて同世代の健康な子どもと変わらないほど歩けるようになった。「弯児はとても賢い子なの。だれか引き取ってくれる人がいて学校に入学できたら、すごい大物になるかも知れないのよ」と労さんは弯児の行く末を心配する。
労秀玉さんはごく普通の田舎町のおばさんだが、思いやりが深く善良な人柄で知られている。長年病床にあるご主人の介護をしながら、ほそぼそと果物を売って、女手一つで家族五人の生計を立ててきた。そんな彼女が捨て子と初めて出会ったのが20年前。ある朝、清掃係の隣人に頼まれて、街頭掃除に代わりに出かけた時のことである。道端に黒山の人だかりができていたので不思議に思ってのぞいてみると、寒風の中に息も絶え絶えな赤ちゃんが捨てられているではないか。人々はふびんに思って見ているだけだった。「かわいそうに」と哀れんではみるものの、引き取ろうとする者は一人としていない。「このまま放っておくと、飢え死にするか、犬やブタに食われるだろう。早く家に連れて帰ろう」。そう思って労さんは赤ちゃんを引き取ったという。
それから彼女は、街頭や病院に捨てられた体の不自由な子どもを引き取るようになった。夫と三人の実の子も生活の保障がないにもかかわらず、恵まれない赤ちゃんの養育を手伝ったという。しばらくすると町じゅうにこの善行のうわさが広まり、労さんの家の前に捨て子を置き去りにする人が増えだした。やがてそこはある種の「特別養護施設」となった。家では赤ちゃんの泣き声が絶えることはない。床の上ではいはいする子やベッドの上で泣き叫ぶ子に引きずり回され、家族中がバタバタ走り回る毎日だった。
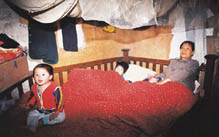 |
 |
実際は、引き取った子どもたちはほとんど助からない運命にあった。それでも捨て子が一人亡くなるとまた一人入る、というように、労さんの家にはいつも十人前後の子どもがいた。「年がら年じゅう泣き声を聞かされて、挙句の果てに死に至る……。こんな不吉なことったらないよ」と親戚や友人、近所の人にひどく疎まれても彼女は動揺しなかった。「哀れな子どもたちも同じ人間。貴い命を授かってきたのです。一人でも助けてあげなければ」
この20年間に、労さんが引き取った子どもは数えきれない。昨年、彼女はすくすくと成長した三人を市の孤児院に入れた。現在家にいるのは弯児、大ノオ、三妹、阿軟と二人の嬰児の計6人。15歳の娘・大サは、まだママの「マ」の字も発音できない。七年前にこの家に連れられて来た時「この子は小児麻痺を患っています。親として手を尽くしましたが結局治らず、わが子を見殺しにする非情の選択をしました……」などと書かれた、涙でにじんだ手紙がポケットにしのばされていた。「実はこの子、癲癇も患っているの。発作を起こすとなると、痙攣しながら地ベたを転げまわるんです」と労さん。ふだんは家の前の置石に日がな一日、ぼーっと座っている。かと思えば驚くほどの大食漢で、昼間は無節操に物を口に運び続ける。夜は失禁するので、彼女の下着やシーツを洗うのが労さんの朝の務めになる。近所の人たちは、これを見て「月に千元(約1万3000円)の給料をくれるといわれてもいやだ」と眉をひそめるが、善良な労さんは顔色ひとつ変えない。「もしかしたら私は、前世でこの子たちに借りを作っていたのかも。この世でできる限りの恩返しをしてあげたい」
雷城鎮は小さな田舎町で、孤児らを収容する福祉施設がない。そのため数年前から鎮の民政局が毎月、労さん一家の大きな子どもに100元、嬰児に30元の補助金をそれぞれ出すようになった。だが100元といっても、大サ一人が使うおむつや洗剤などの代金にすらならない。「労秀玉さんは、子々孫々にまで福を及ぼすかのような善行を積んでいるんだよ」と敬意を抱いている人も多い。だがわが子のことを聞かれると、彼女はいつも切なさで胸がいっぱいになる。彼女は一男二女の母親だが、学費が払えないため三人とも高校を出ていない。とりわけ長男は、結婚二年目に嫁が「こんなに貧しい家でいっしょに暮らせるか」といって家出したため、自暴自棄になって麻薬に手を出し、挙げ句の果てに中毒症が原因で亡くなったという。
「それでも自分がしてきたことを後悔したことは一度もないのよ」と労秀玉さん。苦しい生活の中で、孤児らを抱えて負担はかなり大きいが「これからも愛情を込めて、かわいそうな子どもたちのお母さん代わりを務めていきたい」と力強く語ってくれた。
 |
 |
(2001年2月号より)