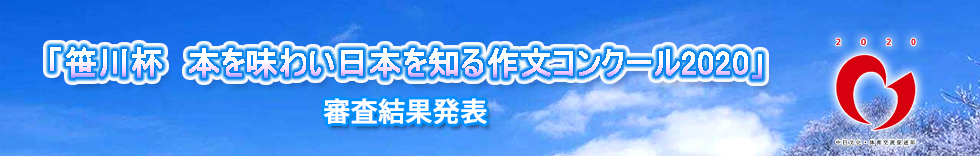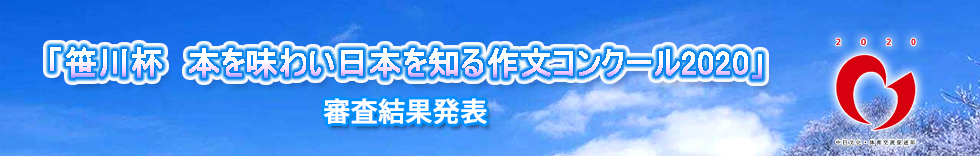劉力暢 遼寧師範大学

「誰かとつながりたくて、広大な海を渡ろうとする人たちに捧げる辞書。それが大渡海です。」映画「舟を編む」の主人公の馬締(まじめ)光也は、人とのコミュニケーションが苦手で、周囲から「変人」と呼ばれている若い男性だ。でも、馬締は言語学専攻なので語彙の量が驚くほど多い。しばしば言葉の正確さにこだわるあまり、話す時に適切な表現を見つけられなくなる。そんな馬締は玄武書房営業部の上司から軽視されていた。しかし、編集部に異動して国語辞典「大渡海」を編纂することになる。
国語辞典を編纂するために、編集部のみんなは毎日言葉を収集して、言葉に意味を加える……普通の若者にとっては大変な仕事だが、馬締は仕事に情熱を持っている。給料も少なく、毎日つまらない仕事だ。しかし、言語学好きの馬締は仕事にやりがいを見つけていく。そして、馬締は段々と変わっていく。言葉の意味を調べるため、人とうまく交流するようになり、社員としても男性としてもだんだん成長していく。恋人までできる。こうして12年が過ぎて、馬締は辞書編集部の編集長となり、国語辞典「大渡海」は多くの困難を乗り越えて出版された。編集部のみんなは、言葉への愛を持ち続け、その後も仕事を続けて、数十年かけてこの辞書を修正していく
どうして、馬締は十五年の青春をかけて「大渡海」の辞書の編纂に没頭したのか。「自分の指先が言葉に触れる。世界に触れる喜びっていうのかな。辞書編集者の醍醐味だ。」これは馬締の言葉である。言葉は常に変化している。新しい言葉が生まれ、言葉の意味は時代と共に変わっていく。その変化を会話や記事から採取するのが、馬締は楽しかったのだと思う。辞書編纂だけではなく、すべての仕事も絶えず変化している。私の憧れの教師という仕事も、教育理念と教授法は学生の変化とともに変化している。学生たちが自分で表現したり、自分の考えをまとめたりする授業が多くなった。学生が自主的に考えて、学習できるようにするためである。教室の黒板はプロジェクタに取って代わられ、さらに、新型コロナウイルスの影響でオンライン授業が始まった。馬締の辞書編集と同じように、教師も常に前に進まなければならない。
この映画を見て、将来、私は学生と共に成長していく教師になりたいと思った。授業以外にも討論会を開いたり、社会実践活動に参加したりして、社会とつながるコミュニケーション力を鍛えていきたい。今、私は大学の外国語サークルで日本語コーナーを企画、実行している。毎回、中日両国の学生に自分の国の文化や流行を紹介してもらう。「日本人の友達ができた。うれしい。」みんなの笑顔を見ると、私も嬉しくなる。外国語のレベルがまだ高くない参加者も楽しく参加できるように、みんなで歌を歌ったり、折り紙を折ったりしている。この経験は私が教師になった時に役に立つと信じている。私も馬締のように一生をかけて、楽しく挑戦していきたい。