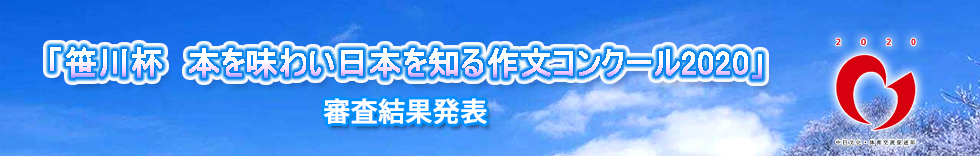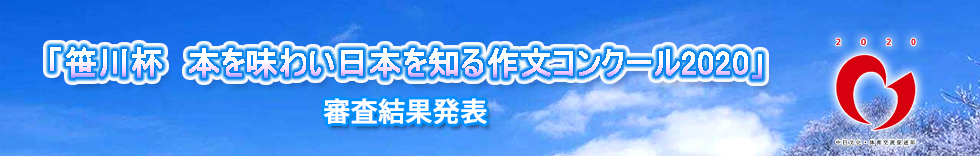李藍宇 対外経済貿易大学

「天才」は羨ましいものだ。
自分は必死に頑張っても「まあまあ」というレベルに達するのに対し、天才はちょっとだけ努力を払って芳しい成績を手に入れることができる。それほどくやしいことはないだろう。私たちはいつか私も成功できるという夢を抱えて奮闘するが、残念なことに、多くの場合にそれは所詮夢である。成功できる人はほんの一部だけだ。その中で「天才」と呼ばれる人はいつも輝かしい存在だ。彼らの前に、平凡な私たちの努力は何の意味があるのか。松本大洋の漫画「ピンポン」を通して私はその答えを探している。
主人公の月本誠はそういうような天才だ。卓球に対して抜群のセンスを持つ彼に、中国のプロ選手も一目置いている。しかし彼は卓球に興味が薄くて、いやむしろ消極的と言ってもいい。確かにこのような個性的な主人公は新鮮に見えるが、私には最も印象的なのは彼のライバルの一人、佐久間学。月本と全く正反対、佐久間は狂うほど卓球に熱中し、毎日一生懸命腕を磨き続けている。「才能と環境はすべてではない。時間が経つと努力も発言権があるのだ」と、佐久間はずっとそれを信じている。にもかかわらず、現実は残酷なものだ。必死に練習した甲斐もなく、彼は天才の月本の前にただ惨敗を喫する始末だ。佐久間の信仰が揺らぎ始めた。「どこが違うんだよ!なんでお前だよ!俺は努力したよ!お前の10倍、いや、100倍、1000倍したよ!それこそ朝から晩まで卓球のことだけを考えて、卓球にすべてをささげたんだよ!」月本への怒鳴りというより、むしろ彼は自分を責めているように見える。「それは佐久間が才能がないからだ。」と、月本から平気で吐いた一言に佐久間は閉口した。そうだ、彼らは自分の能力を常に自覚している、「天才」はそういうものだ。それに対し、凡人の私たちは自分の限界をはっきり認識する前に決して断念せず、ひたすら前に進んでいく。天才との差を直面し、さらに失敗の運命を受けざるを得ない時もある。それは苦しい過程だ。
だが、そういう「凡人」はむしろすごい存在だと私は思う。確かに失敗と劣等感は苦しいものだが、よく考えてみると、天才が相手になるだけに苦しい思いをするのではないか。佐久間も、彼は一生懸命努力したこそ、天才と競争できるほどのレベルに達したのだろう。
ギリシア神話でシーシュポスは神から罰を受け、巨大な岩を山頂に上げようと命じられた。毎回あと少しで岩が届くと、岩は麓に転がり落ちてしまい、彼はまたゼロから運び上げるしかなかった。生まれつきの才能の前に、その努力は「シーシュポスの岩」のような徒労かもしれない。だがたとえ徒労でも、たとえまたゼロから始めようとも、そこで振り返ってみると、「私だってここまで来たのか」と、その努力には価値がある。
むしろ、努力そのものは平凡な私たちが持っている最も貴重な才能と言えるだろう。