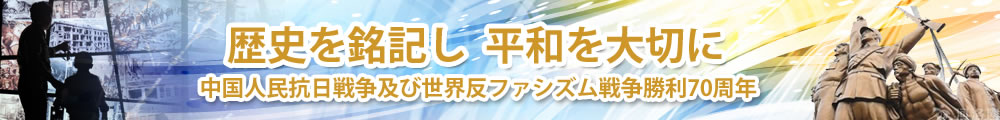 |
| 浅野勝人・元外務副大臣 「平和と友好の精神を受け継ぎ、中日の共同発展を促進」 |
|
今年は抗日戦争勝利70周年にあたる。戦争経験者の声に耳を傾け、歴史を回顧し、反省してこそ、未来に向かうことができ、中日両国の平和友好・共同発展を促進することができる。日本の浅野勝人・元外務副大臣は、戦争経験者であると共に、中日両国が友好の門を開いた瞬間を見届けた歴史の体験者でもある。浅野氏は人民網の取材に対し、「両国関係の発展は、両国の先代の政治家の中日友好の精神を受け継ぐべきである。中日両国が、どんなに考え方が違っても、どれほど大きな対立点を持っていても、武力でそのことを解決するのは許してはならず、戦争は二度と許してはならない。両国交流の強化は両国関係発展の近道だ」との見方を示した。 1938年生まれの浅野氏は幼い頃、米軍の爆撃および戦後の貧困を経験した。早稲田大学を卒業後、浅野氏はNHKの政治記者となり、記者として1978年の「日中平和友好条約」調印という歴史的な出来事を体験した。浅野氏はその後、政界に進出し、衆議院・参議院議員に当選。橋本内閣の防衛政務次官、森内閣の外務政務次官、第1次安倍内閣の外務副大臣、麻生内閣の内閣官房副長官を歴任した。政治記者として中国関連の報道を担当したことをきっかけに、浅野氏は中国と深い縁を持つようになった。浅野氏は多くの中日交流活動に参与し、外務副大臣だったころには中日文化・スポーツ交流活動の開催を担当したこともある。 浅野氏は、中日両国の先代の政治家たちが中日関係の発展のために並々ならぬ努力をしてきたことをよく知っている。1974年、中日両国の直行便開通に関する交渉の際、浅野氏は同行記者として当時の大平正芳外相らと共に初めて中国を訪れた。当時、両国には直行便が開通しておらず、両国の人的往来は非常に不便だった。直行便の必要性を強調するため、大平外相は記者らと共に、特別機を使用せず、汽車を乗り継いで北京まで行くことにした。浅野氏は政府関係者らと共に香港に向かい、そこから深センの羅湖口岸を通じて中国に入国した。深センから汽車で広州まで行き、数日後にようやく北京に到達した。浅野氏は、「以来、周恩来総理は大平氏の誠意ある人柄を理解し、2人の間には信頼関係が築かれた。2人はそれから何度も様々な問題を協議したが、素晴らしい人間関係だった」と語る。 浅野氏は取材の中で、幾度も周総理や大平外相など、先代の政治家に言及した。浅野氏はこれらの政治家の中日関係に対する先見性と誠意、そして彼らの人間的な魅力に心服させられたという。「幸運なことに、周恩来総理に接見していただく機会に恵まれた。周総理の中日関係発展に関する言葉は、かけがえの無い誇りと指針となり、今でも心に生きている」。浅野氏は2010年に政界を引退した後も、中日交流事業に力を注いだ。2011年以降、招きに応じて北京大学で7回にわたる講演を行い、学生たちに自らが体験した中日関係の発展の歴史を語り、中日友好への期待を伝えてきた。浅野氏はこうした交流を「草の根の交流」と呼ぶ。中日国交正常化に立ち会った1人である浅野氏は、先代の政治家たちが中日関係のために行った貢献を中日両国の若者に伝え、若者たちが「温故知新」し、そこから何かを学び、中日関係に正しく向き合い、素晴らしい未来を創造することを望んでいる。今年5月、浅野氏は北京大学など中国の大学で8度目となる講演を行った。 同世代の多くの人と同じように、戦争は浅野氏に辛い記憶をもたらした。日本が降伏した1945年、浅野氏はちょうど小学一年生だった。浅野氏は当時を振り返り、「当時、日本の主な都市はほとんどが米軍の爆撃を受けた。私の故郷・愛知県豊橋市も例外ではなく、2つ年上の兄と祖母と手をつないで、その戦火を逃げ惑ったのを今も記憶している」と語る。 戦後、ほとんどの日本人は貧困を経験した。「当時はお米がなくてイモばかり食べていた。アメリカが援助した学校給食の粉ミルクが唯一の栄養源だった。それが後になって、家畜用の脱脂粉乳だったことがわかり、敗戦国の立場を思い知らされた」。 浅野氏は「戦争というものは、勝っても負けても犠牲になるのはその国の市民。互いに、どんなに考え方が違っても、溝があっても、どれほど大きな対立点を持っていても、武力でそのことを解決するのは許してはならないし、間違っている。私たちの世代は、戦争は二度と許してはいかんという思いが強い。最近日本の世論が右傾化の傾向にあることを懸念している」と語る。 浅野氏は「今後の発展を促進するには、歴史問題を総括しなければならないが、戦後の日本国内では、戦争責任について十分な議論が行われなかった。戦争責任の曖昧化によって、日本国内の一部の人の歴史認識に誤りが生じた。1950年の朝鮮戦争が勃発し、米軍の軍需調達による特需は確かに日本経済復活のきっかけになった。一方で、戦後の冷戦構造の中で起きた朝鮮戦争は、日本の戦争責任を曖昧なまま放置してしまう原因になったという側面もある。徹底した非軍事化が米国の占領政策の基本だったが、朝鮮戦争を有利に進めるため、日本の協力体制を作るために、政策転換があり、職務を解かれていた一部の政治家が復帰した」と指摘、さらに「歴史認識をめぐって日本国内には様々な見方が存在する。村山談話や河野談話はこの曖昧さにけじめをつけるという意味で、過去との決別を明確にしようと発表された試みであり、継承されるべきだ。安倍首相の70年談話が、過去をレトリックでごまかそうとするのではなく、明快率直に過去と向き合って、過去にけじめをつけ、アジアの人々の心配懸念を払拭するような理念の表明になってほしいと、期待している」と述べた。 中日関係の今後の発展について、浅野氏は「中国のGDPはすでに日本を抜き、世界2位の経済大国となったが、日本には中国が参考にできる点がまだある。中国は日本の後を追うように、超高齢社会に突入する。中国経済がこれから直面する問題は困難かつ重要だ。それをお互いに克服するためには両国が様々な分野で協力すべき。そうすることで相乗効果が生まれる。アジア太平洋地域のパワーバランスには変化が生じており、日本も安保政策を調整している。しかし日本は戦争に参与しないという国策を堅持し、安保政策の調整について隣国にしっかり説明する必要がある」と述べた。 浅野氏は最後に、両国の若者への期待として「戦争体験がないという意味では日中の若者は同じ。しかし、日中の若い人たちに言いたいのは、今のこんなに幸せで安全な生活は、戦後70年間平和が続いてきたから。平和は努力しないで得られるものではない。互いがしっかり近隣諸国の人々をいつくしみ、心の底から手を握り合うことが平和を創造すること」と述べた。(編集SN)
「人民網日本語版」2015年7月7日
|
| 人民中国インタ-ネット版に掲載された記事・写真の無断転載を禁じます。 本社:中国北京西城区百万荘大街24号 TEL: (010) 8837-3057(日本語) 6831-3990(中国語) FAX: (010)6831-3850 |