さようなら、安さん
王衆一=文 宋菲=写真提供

安淑渠さん
1月18日、安さんが亡くなった。安さんの遺志に従い、葬儀は親族だけで執り行った。しかし追慕の念は抑え難く、何かしなければならない。1989年に人民中国雑誌社に入った私は、安さんが受け持っていた翻訳部に配属され、安さんからさまざまな指導を受けた。記憶がよみがえり、安さんのエピソードを書いてみんなと分かち合おうと思った。すぐかつて安さんの同僚だった劉徳有さん、安さんのお嬢さんの宋菲さんに連絡し、貴重な資料を提供していただき、細かな記憶を確認した。これで安さんの物語をいよいよはっきりと浮き彫りにできるようになった。
安さんは30年に大連で生まれ、フルネームは安淑渠という。本籍は山東省煙台で、きつい膠東(山東半島渤海湾沿岸)なまりの標準語を話した。中国人と日本人の同僚たちはこの全く偉ぶらない副編集長を「安さん」と親しみを込めて呼んでいた。52年、『人民中国』日本語版の創刊のために安さんと同時に大連から北京に転任した劉徳有さんは次のように回想する。「安さんのお父さんは大連で茶葉店を開いていました。安さんは日本人が大連で運営していた小学校に通い、卒業後は旧制中等教育学校の大連神明高等女学校に入学しましたが、3年生の時に日本が降伏し、学校は閉鎖されました。45年に日本の植民地統治が終わった後、大連はすぐに解放されました。老安は『文科専業学校』に移り、卒業後は大連日報社で記者になりました」。その後、52年に『人民中国』日本語版の康大川・初代編集長が大連の若者4人を北京に異動させた。劉徳有さんによると、同時に外文出版社(中国外文局の前身)人民中国編集部日本語部に異動してきたのは彼と安さん、李玉銀さん、于鴻運さんだった。
『人民中国』2009年6月号は中国外文局創立60周年の記念特集を組んだ。安さんは「『人民中国』の生みの親、康大川」という回想記を執筆し、愛情を込めて草創期の苦労や逸話を盛り込んだ。記事には2点の写真が付けられた。1点は1955年、雷任民・対外貿易部副部長を団長とする中国貿易代表団が訪日した時の写真だ。康さんと安さんも同行し、通訳だった安さんは康さんらに付き添って岩波書店を訪問した。当時、『人民中国』日本語版は2周年を迎えたばかりで、康さんも安さんもまだ若かった。もう1点は、安さんと丘桓興・元副編集長がアルバムをめくり、康さんと共に働いた日々を振り返っている写真だ。丘さんも1月10日に病気でこの世を去った。中日国交正常化50周年を迎える今年、また1年後に『人民中国』日本語版創刊70周年を迎える今年、2人の大先輩が相次いで亡くなったことは嘆き悲しむほかない。
52年に『人民中国』に移ってきた時、安さんは22歳の若さで、最初はアートディレクターを務めた。具体的にはレイアウト、組み版、イラスト・写真選定で、校閲も担当した。同僚には瀋陽の民主新聞社から来た日本人で、組み版と校閲に長じた岡田章さん、校閲の達人である李薫栄さん、安さんと同時に大連から来た李玉銀さん、日本人アートディレクターの池田寿美さんがいた。

安さんによる回想記「『人民中国』の生みの親、康大川」の誌面
安さんは回想記に次のように書いた。「二回の試験的発行に続き、インクの香りの漂う『人民中国』(日本語版)が誕生した。みなが祝杯を挙げようとしていたその時、突然、大きな叫び声があがった。『ちょっと待て!』。一人の日本人の名前が間違って印刷されていたのだった。当時は鉛の活字を組んでおり、誤植の修正のためには、印刷された雑誌の誤字をナイフで削り、正しい鉛の活字を印鑑のように一つ一つ修正場所に押していく必要があった。みなが総出で、二十四時間かけてすべてを修正した。この出来事は『読者のために責任を負い、少しもおろそかにせず』という教訓を残した」

1955年の訪日は安さん(中央)にとって初めての通訳としての随行

ホテルテートのベランダに立つ安さん、康さんと劉さん(左から)
多士済々の編集環境の中で、また民間交流を繰り広げた活動の中で、安さんはレイアウトと校閲の名人になっただけでなく、特に優れた翻訳者・通訳者へと急速に成長した。55年の訪日は安さんにとって初めての通訳としての随行で、同行の通訳には劉徳有さんもいた。訪日期間中、康大川さんは岩波書店を訪問し、日本の出版業について考察した。劉さんの回想によると、康さん、劉さん、安さんの3人が一緒にフレームに収まったこの貴重な写真は、皇居と堀が見えるホテルテートのベランダで撮影された。

1955年8月、劉寧一氏の通訳として、日本で第1回原水爆禁止世界大会に参加した安さん(右から2人目 )
55年8月、第1回原水爆禁止世界大会が日本で開かれた。世界平和を守り、核兵器による威嚇とどう喝に反対するため、劉寧一氏(後の中国共産党中央書記処書記)が平和擁護世界大会中国代表として訪日し、安さんが通訳を務めた。この代表団は中国からの声を日本に伝え、被爆者と交流し、各界の人々と幅広く付き合った。民間外交の形で中日関係の正常化を推進するための土台となる仕事をした。部落解放運動の指導者、松本治一郎氏から贈られた記念品は今も保管されている。このことからも当時の代表団の幅広い交流が見て取れる。

1963年11月5日〜12月3日の中国作家代表団第4回訪日活動で通訳を務めた安さん(左端)
50〜60年代の多くの訪日活動のうち、63年11月5日〜12月3日の1カ月近い中国作家代表団第4回訪日活動で、通訳の安さんは貴重な写真を比較的多く残している。この年の2月、対日交渉を受け持っていた廖承志氏は『人民中国』に対し、編集方針を調整し、文化的な内容を充実させ、読者を増やすよう要求した。6月、『人民中国』創刊10周年を記念するため、当時の外文出版社の訪日団が日本に渡り、読者や発行者、作家らの意見を聞き、編集方針の修正、社会・文化・市民生活分野の報道の拡充のため、着実な考察を行った。年末の作家代表団の訪日は、日本との文化交流強化事業の一環としてセッティングされたものだ。現存する貴重な写真からは、この訪日で巴金氏や冰心氏ら中国人作家と日本人作家が深く幅広く交流し、相互理解のために重要な役割を果たしたことが分かる。
60年代半ば以降、安さんは巧みな日本語をよりどころに、直接日本語による取材と執筆をこなすようになった。彼女は『人民中国』の編集・翻訳一体化の先駆けだった。72年、長年の努力にようやく光が当たった。この年の9カ月間、安さんは外交部(日本の省に相当)の田中角栄首相受け入れチームに出向し、翻訳グループのリーダーに任命され、中日国交正常化の歴史的瞬間を目撃した。安さんの生前の回想によると、出自が原因で農村に下放していた母親が重病だったが、自分は重要な仕事を抱えているために付き添えなかった。母親の最期をみとれず、彼女は一生悔やみ続けた。

1974年、鄧小平氏は北京で日本婦人科学者訪中団と会見し、安さん(後列右端)は通訳を務めた
国交正常化以降、安さんはより忙しくなった。74年2月28日〜3月26日、安さんは再び出向し、日本婦人科学者訪中団の北京・広州訪問の全行程に同行した。1カ月近い付き合いの中で、婦人科学者らは安さんの行き届いた配慮や立派な通訳に感服し、後日わざわざ連名で手紙を書いて感謝した。当時は鄧小平氏が返り咲いてから丸1年になり、国が科学教育の立て直しを進めていた時期で、1年後には周恩来総理が第4期全国人民代表大会で「四つの近代化」を再び提唱した。こうした背景の下、鄧小平氏は北京で日本婦人科学者訪中団と会見し、安さんは同行通訳として鄧小平氏のために通訳した。これは『人民中国』にとって栄誉ある出来事になり、私の入社後もしばしば語られていた。ある時、私は仕事の合間の会話で、好奇心から安さんに「安さんの日本語は一流で全然問題はないですが、そのきつい膠東なまりと鄧小平さんのきつい四川なまりとの間でコミュニケーションは全く問題なかったのですか?」と尋ねた。安さんはこのような問題を考えたことがなかったようで、少し思い起こしてから答えた。「コミュニケーション全体はとても順調で、なまりの影響はありませんでした。まず、鄧小平さんの話は筋道が通っていて聞き分けやすいですね。次に、鄧小平さんは見聞が広く、全国津々浦々の幹部と付き合っているので、膠東なまりぐらい聞き取れるに違いありません」
副編集長になった後も安さんはざっくばらんな仕事ぶりを維持し、各方面の意見をうまく聞き取り、読者や顧問との意見交換を特に重視した。重要な客や愛読者訪中団が訪ねてくるたび、安さんはいつもほかの役員と共に熱心に来客と懇談し、謙虚に教えを請い、意見を交換した。

日本の読者を訪ね、心からの歓迎を受けた安さん
ある年の国慶節の連休、1人の読者が社を訪ねてきて、安さんは自ら接待し、深く交流した。また、独身寮に住んでいた私をこの読者に付き添わせ、祝日の北京を見学してもらった。私たちが連休を犠牲にして手配したことを知り、突然訪ねてきたこの読者はとても感動し、自分の唐突さに恐縮しながらも、人民中国の周到な接待にしきりに感謝していた。接待の仕事が終わった後、安さんは私の休日を邪魔してしまったと感じ、わざわざ私を自宅に招き、ちらしずしを作ってねぎらってくれた。神宮寺敬夫妻、水原明窓顧問、勝田弘さん、林謙三さん、白鳥良香さん、西野長治さんら、日本各地の読者会の代表や一般会員の方々など、古くからの多くの読者は安さんのこうした人望によって『人民中国』と長期的なつながりを保っていた。安さんが日本の読者を訪ねた時も、読者の心からの歓迎を受けた。
私が『人民中国』に加わった時、安さんはすでに定年退職の年齢に近づいていた。安さんの指導の下で働いたのはわずか3年余りだったが、常にその影響を受け、多くの役立つ知識や方法を学んだだけでなく、精神的にも洗礼を受け、一生の財産になった。『人民中国』のタイトル会議は翻訳部を中心とし、中日の同僚が最初から最後まで日本語で議論する。これは異文化交流の意識を育み、翻訳をいっそう受け手の思考に近づける点で重要な意義を持つ。安さんが参加すると、会議の雰囲気は特に活気づいた。議論が思考を刺激し、生き生きとした一つ一つのタイトルが決められていった。この伝統は『人民中国』で今も受け継がれている。
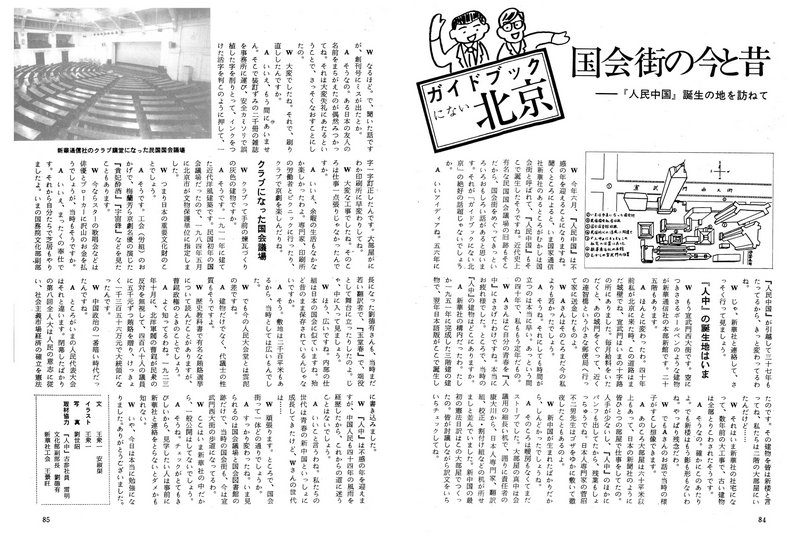
コラム「ガイドブックにない北京」の誌面
93年に『人民中国』は創刊40周年を迎えた。仕事の都合で定年を延長していた安さんも、退職を迎えようとしていた。当時の私は「ガイドブックにない北京」というコラムの企画と取材・編集を担当していた。そこで私は『人民中国』誕生の地に関するスペシャルリポートを思い付いた。創刊スタッフの中でまだ職場にいたのは安さんだけだったためか、彼女は大いに賛成してくれた。キャリアを終えるに当たり、かつての自分のスタート地点を再訪したいと思ったのかもしれないし、若手に伝統を伝えたいと思ったのかもしれない。安さんは私と一緒に新華社内の国会街の取材に行くことを決めた。国会街に着くと、当時の建物はすでに跡形もなく消えていた。安さんは感慨深げな様子で、情熱に燃えていた草創期の日々を思い起こし、いろいろ面白い話を教えてくれた。記事は対談の形で仕上げられ、日本語原稿の完成後、安さんにチェックを依頼した。戻ってきた原稿には安さんが赤ペンで真剣に修正した跡が残っていた。それでも安さんはとても謙虚に自分の署名を後ろにすることにこだわった。私はこの修正原稿をずっと保存していたが、社の数回の移転後に所在不明になってしまい、今でも残念に思っている。
創刊40周年の記念レセプションは西苑ホテルで盛大に開催され、多くの日本人読者と同業者グループが祝福してくれた。安さんはこの時、日本からの古い友人たちと一堂に会し、楽しかった出来事を共に振り返っていた。レセプションでは、楊正泉・中国外文局局長が安さんに栄誉証書を授与し、彼女が生涯をかけて果たしてきた傑出した貢献を表彰した。
定年退職以降の30年近い間、安さんは『人民中国』の発展に常に関心を持ち、常にアドバイスしてくれていた。多くの長年の読者は依然として安さんのことを覚えており、私が仕事で訪日して読者に会うたび、必ず安さんの近況を尋ねてくる方がいた。安さんは晩年を娘と過ごし、静かな暮らしを楽しんでいた。新中国の歩みに付き従い、志ある仲間と共に1冊の雑誌によって中日両国の人々の心の懸け橋を築いた安さんは、歩んできた道を振り返ると幸せだったはずだ。彼女は中日関係が戦後に困難の中で歩み出し、一歩一歩国交正常化を迎えたのを目撃し、中日関係が相対的に最も良好だった時期に定年退職した。
安さんのエピソードは『人民中国』の初心の在りかを教えてくれる。その世代に特有の純粋さ、使命感、献身的な姿勢、プロ意識こそ、私たちが今日において受け継ぐべき最も貴重な財産だ。今年は中日国交正常化50周年で、『人民中国』は来年創刊70周年を迎える。残念なのは、安さんがこれら記念すべき時期の到来を待たずに世を去ったことだ。さようなら、安さん! どうかかの世でも私たちを見守ってください。生涯をささげた『人民中国』の未来を見守ってください。